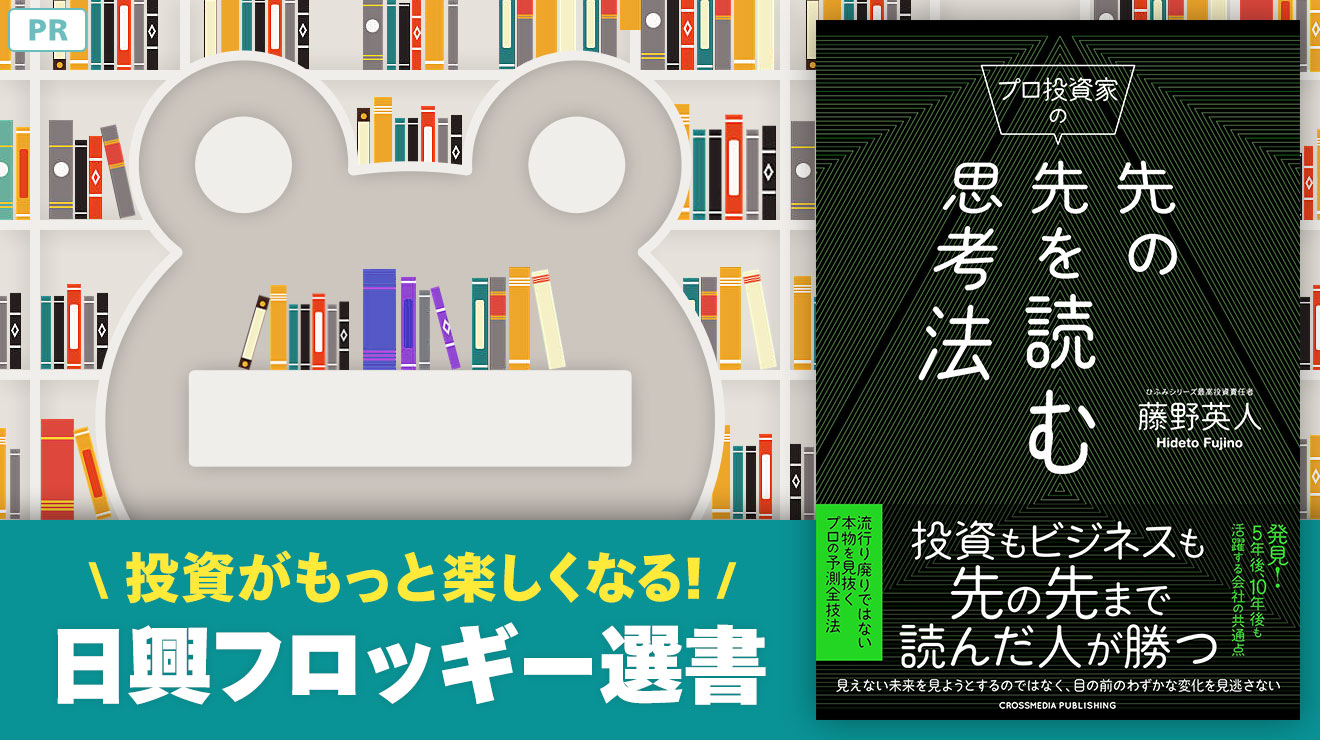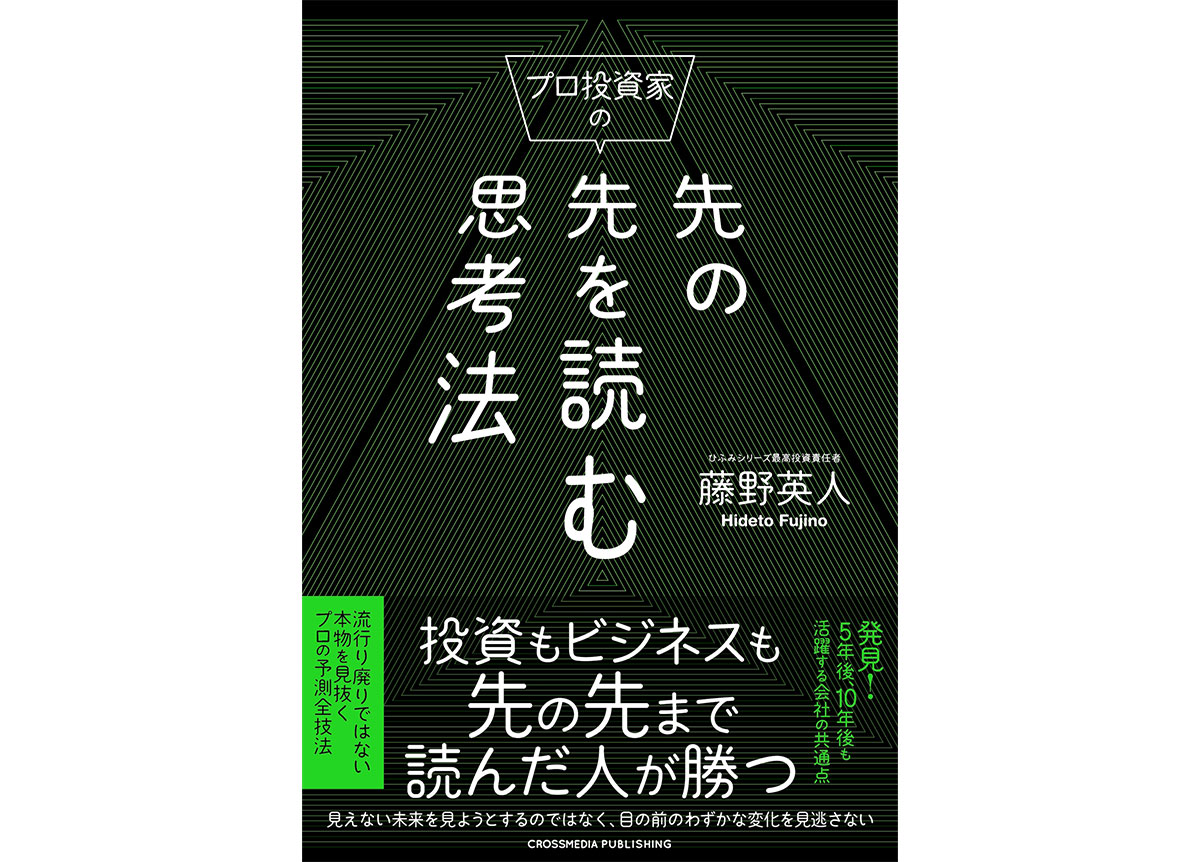投資や資産形成をもっと楽しくするためにピッタリの書籍を、著者の方とともにご紹介する本連載。第1回・第2回では、「先の先」を読むための考え方やトレーニングを紹介しました。今回は、著者の藤野英人さんが普段から行っている「情報収集と思考の熟成の手法」を見ていきます。[PR]
脳の奥底で200のことを同時に考え続ける
私は、「情報収集」や「実際の体験」を通じて、つねに「先の先」を読むための材料を集めています。限られた時間の中で、より多くの材料を集めるためには、工夫も必要です。ここでは、その工夫の一端を紹介したいと思います。
一つは、なにかを真剣に考えたりじっくり見たりしたあと、いったん考えるのをやめ、そのまましばらく放っておくことです。
もちろん、本業である投資家としての仕事は毎日継続しており、放っておくことはありません。しかし、周辺の仕事や趣味のことなど、その他の関心事については、毎日考え続けているわけではないのです。
一度でも真剣に考えたり、じっくり見たりしたものは、放っておいても脳の奥底に眠っています。パソコンで言えば、スリープ状態になっているようなイメージです。そして、人との会話など、なにかの刺激があると、それがむくっと再起動するのです。
面白いことに、趣味の話をしているときに講演の話のネタを思いつくといったように、直接関係のある話をしていたわけではなくても、ポンと答えや新しい気づき、アイデアが出てきたりするのです。これは、もともと「脳の奥底に眠っている関心事」が、つねに200か300くらいはあるからかもしれません。
人と話すことで「関心事」が再起動する
人と会話することは、重要な情報収集法の一つです。
例えば、非常に優れた経営者として尊敬しているSHIFTの丹下大社長と面談していたときのことです。丹下さんが「私はジャイアンだ」と言ったところから、「たしかに丹下さんはジャイアンに似ている。ではジャイアンとはなにか?」という話になりました。
これはただの雑談だったわけですが、話しているうちに、「じつはジャイアンってすごいんじゃないか」「ジャイアンの力は、腕力ではなく『巻き込み力』では?」と話が発展していったのです。
ジャイアンは、チームを組成して台風のように人を巻き込み、プロジェクトを推し進めていきます。ここでいうプロジェクトとは、遊びかもしれませんし、ジャイアンリサイタルかもしれませんし、冒険かもしれません。しかしいずれにしても、ジャイアンの魅力は「巻き込み力」だということで意見が一致しました。
そのとき私は、以前に考えて「脳の奥底に置いていたこと」の答えの一つを見つけたのです。それは、リーダーシップの本質はジャイアンの「巻き込み力」にあるのではないか、という気づきでした。
いずれにしても、私が以前に真剣に考えて意識下においていた「リーダーシップとは?」という問いが、丹下さんとの会話によって再起動したわけです。
走りながら情報収集。60分の時間を3倍に活用する
流行や異国の文化、価値観などを知るための情報収集法として、私は映画もたくさん観ています。そのための時間をどうつくっているかという話です。
コロナ禍でライフスタイルを見直す中、私は週に2、3回ジムに行ってトレッドミルで走るようになりました。アップルウォッチの心拍計を使い、走った距離、ペース、心拍数の上がり方などを記録して、心肺機能がどれくらい向上しているのかをチェックしながら継続しています。
最初の頃は走る時間は40分ほどでしたが、心肺機能が上がり、今では1回60分走っています。これが週3回となると、だんだん時間がもったいないと感じるようになってきました。もちろん体調管理のためには、週に3時間走ることに大きな価値があることはわかっていますが、インプットもアウトプットもない時間になってしまうのはちょっと残念です。
そこで始めたのが、トレッドミルで走っている時間にiPadで映画を観ることです。
映画は英語圏のものに絞り、字幕表示も英語にします。これなら、映画を観てさまざまな知識を得たり、多様な人々の考え方や価値観を知ったりしながら、トレーニングで心肺機能を向上させると同時に、英語のリスニング力を鍛えることもできます。
実際にiPadで映画を観ながら走るようになってわかったのは、映画に惹き込まれると運動のつらさがだいぶ軽減されるということです。走る時間が楽しくなったことは、大きな収穫でした。
またリスニングのトレーニングとしての効果も感じています。映画は映像や音楽によってその場面でなにを描いているのかを推測することができますから、知らない表現が出てきても、そのシーンの状況から意味を把握しやすいのです。
もちろんわからないフレーズもありますが、20分走ったら1分休んで水を飲むことにしているので、その時間を活用してiPhoneで意味を確認することもできます。60分の時間を3倍に活用するこのやり方は、最近の私のお気に入りです。
並行していろいろやることで、学びが化学反応を起こす
実際の体験を通じて学ぶという点について言えば、私はよく「ずいぶんいろいろなことをやっているんですね」と驚かれます。これは私が「多くの分野に挑戦して8割の出来を目指す」という戦略を持っているからです。
日本では、一つのことに集中してそれを極めるのがよしとされる傾向があります。私自身は高校時代から複数の部活動をかけもちしていましたが、一般には部活も一つに絞るのが当たり前になっているのではないかと思います。
仮に子どもが、「サッカー部と陸上部と将棋部をかけもちしたい」と言ったとしたら、「あれこれ同時に手を出したらすべて中途半端になってしまう」といい顔をしない大人が多いのではないでしょうか。
もちろん、一つの分野で完璧を目指すのも素晴らしいことです。しかし複数の分野で「8割の出来」を目指すことにも、大きな意味があると私は思います。
さまざまなことにチャレンジすると、梃子(てこ)を使うように学びの幅を広げることができます。「学びにレバレッジをかける方法」という点で大きな意味があるわけです。
当たり前ですが、私自身、やってみたことがすべて8割できるようになっているわけではありません。それでもいろいろなことにチャレンジし続けているのは、すぐに結果を求めず、長期ビジョンでやってみようという意識があるからかもしれません。
必要なのは、「なにかをやってみれば、それがいつかどこかで別のなにかに結びついて化学反応を起こし、花開くこともある」という確信です。この確信があれば、ちょっとやってみて結果が出なくても、ストレスに感じることはないでしょう。
学ぶときは「最初」に集中するといい
ただし、新しいことにチャレンジするときは「学びの最初だけ集中する」ということを意識しています。
「学ぶ」というと、一般には継続することが最も重視されますが、私が考える重要ポイントは「初速」です。「最初に勢いをつけてたくさんの新しい情報を吸収し、そこからペースを落として長く続ける」というアプローチであれば、次々に学ぶ対象を増やしていくことができるからです。
例えば、私は社交ダンスを習っているのですが、始めたのは15年ほど前でした。当初は週3回ペースで通い、3カ月ほど経ってから、週1回、2週間に1回……というように徐々に頻度を落としていきました。
初期段階は次々に自分にとって新しいことが出てくるので、そこでぐっと集中したほうが何事も習得は速いでしょう。ここである程度まとまった時間を割くと、成長カーブをうまく立ち上げることができます。そうやってある程度の期間を経て基本的な技能を身につけたら、そのあとは「長く続ける」ことが意味を増してきます。
もちろん「集中してやること」と「長く続けること」を掛け算できたほうが、高みを目指しやすいことは間違いありません。しかし1日は24時間しかありませんから、すべてのことをプロ並みにやるというのは現実的に不可能です。
主従で言えば、私の場合は投資家という仕事が「主」であり、ほかのものは「従」ですから、「従」については割ける時間が限られます。「従」については「ある程度できればいい」と割り切り、細く長く続けていければいいと考えているのです。