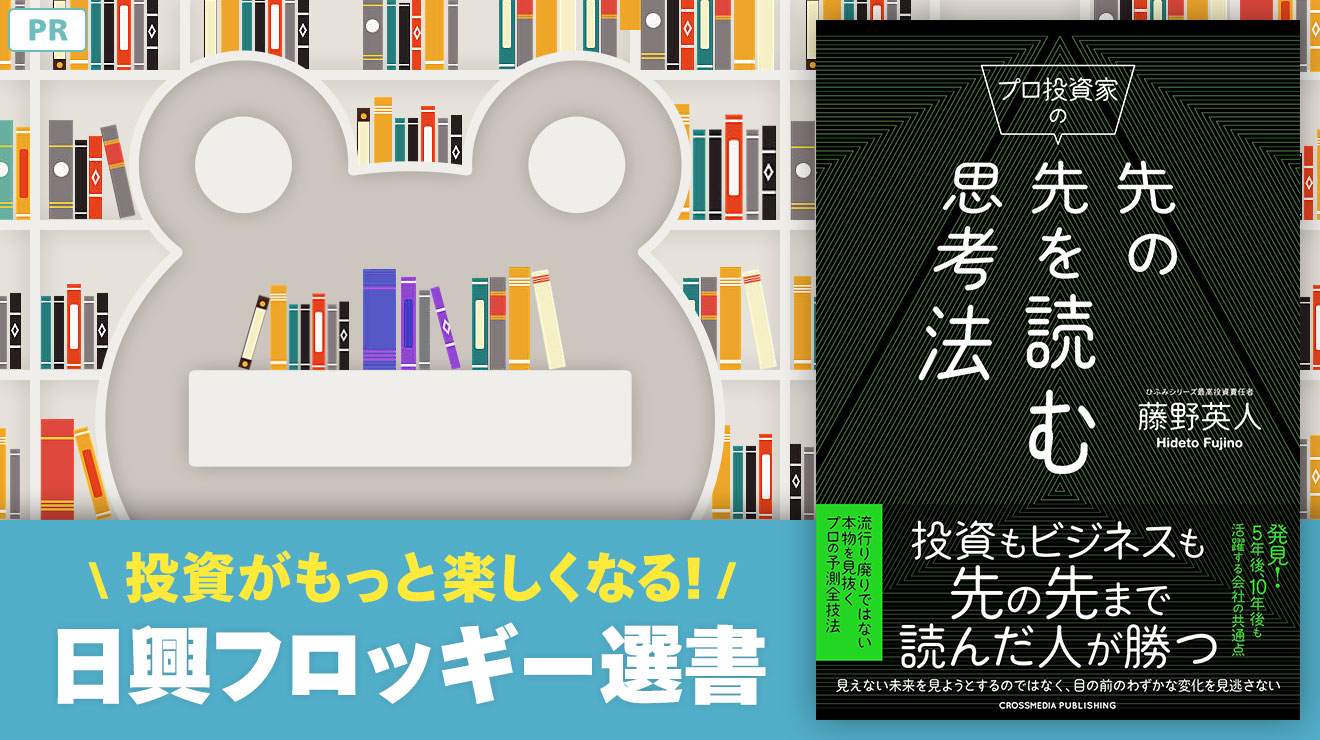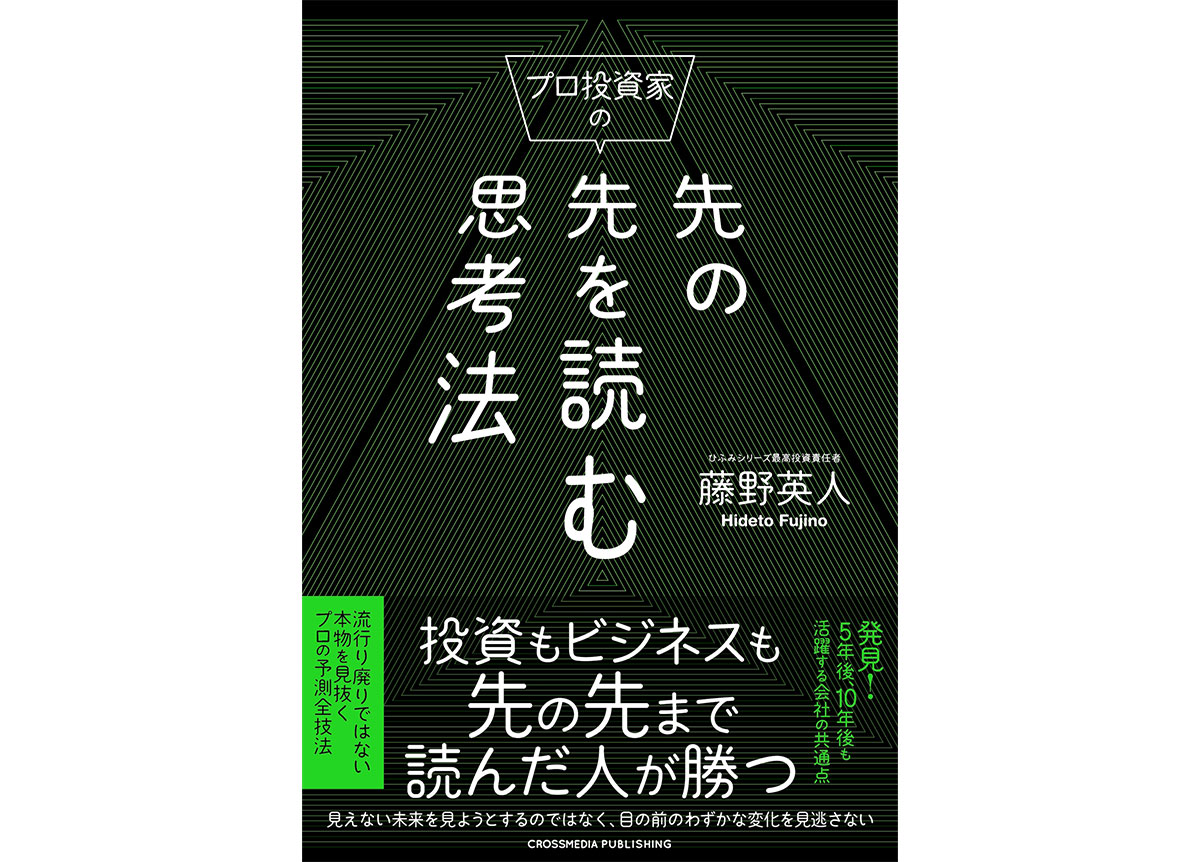投資や資産形成をもっと楽しくするためにピッタリの書籍を、著者の方とともにご紹介する本連載。前回は、先の先を読むためには「小さな変化を捉えること」が重要だとお話ししました。今回は、そのために著者の藤野英人さんがしている「知的トレーニング」を見ていきましょう。[PR]
私が3万人のツイートを読み続ける理由
「先の先」を読んで思考するためには、まず「今」を深く広く知ること、つねに自分をアップデートし続けることが重要です。そしてそのためには、「多方面からの情報収集」や「多角的な思考」が必要です。ここでは、私がそのために実践していることをご紹介したいと思います。
私がしているトレーニングの一つは、Twitterでフォローしている3万人ほどの人たちのツイートを読むことです。
自分でTwitterに投稿することをやめてずいぶん経つのですが、1日か2日に一度ほどはTwitterを開き、5分か10分ほど、高速で流れていくツイートを拾い読みしています。フォローしている3万人は、なるべくランダムに選びました。自分と趣味が似ているとか思想が近いといったこととはまったく無関係に、どちらかといえば年齢や性別、学歴、居住地域などができるだけ多様になるようにフォローしています。
つまりTwitterを通して、「さまざまに異なる属性を持つ人たちが日々どんなことをつぶやいているのか」を定点観測しているわけです。とくに世の中で大きなイベントがあったときは、多くの人が同じイベントについてつぶやきますから、「起きたイベントに対してどのような感情が起きうるのか」を知るためのサンプリングとしてツイートに注目します。
Aというイベントに対して、面白いと思うか不快に感じるのかは、人によって異なるのが当然です。そこに善悪があるわけではないのです。だから、自分の感じ方や考え方と比較して「正しい」「間違っている」などと判断することはありません。
このような姿勢で3万人のツイートを眺めていると、「世の中の人が全般的にどう思っているのか」「この属性の人はどう考えることが多いのか」といったことがおぼろげながらつかめてきます。すると、自分と属性の異なる人とコミュニケーションができたり、世の中のトレンドが見えたりもするのです。「この商品・サービスが世間で受けるか受けないか」といった予測も、当たる確率が高まります。
深夜のレストランで生活者の本音を拾う
「SNSなら自分もよくチェックしている」という方も多いと思いますが、気をつけなければならないのは、SNSの多くが、その人の趣向に合わせて表示をカスタマイズしていることです。
ビジネスという面でSNSを見れば、利用者にとっていかに快適な空間を作るか、その快適な空間の中でいかに趣向に合わせた広告を表示させて、それをクリックさせるかが重要です。そして、そのための手法は、AIを駆使することによってどんどん洗練されているのです。
「エコーチェンバー」と呼ばれる現象がさらに進んだ結果、例えば「右寄り」の人が見ているFacebookの世界は右寄りの人ばかりが、「左寄り」の人が見ているFacebookの世界には左寄りの人ばかりがいるということになります。利用者はその居心地の良い空間で「自分がFacebookで見ているものが世界の実像を示している」と思い込んでしまったりします。
ですから私は、SNSではなるべくランダムに多様な人のものの見方や価値観に触れることを意識していますし、SNS以外にリアルな世界で人をウオッチすることも大事にしています。
私がコロナ禍の前に住んでいた東京のマンションのすぐ近くには、ファミリーレストランの「ジョナサン」があり、以前はそこでよく周囲を観察していたものです。
ドリンクバーを頼み、コーヒーなどを飲みながら1、2時間ほど過ごして周囲の会話に耳を傾けると、勉強になることがたくさんありました。あるときは、「パパ活」をしていると思しき若い女性と中年男性が待ち合わせしているのに出くわしたこともあります。そうすると、会話の内容からパパ活の仕組みがわかったりするわけです。
都心のジョナサンの面白いところは、ブルーカラーもホワイトカラーも空間を共にしていることです。海外の場合、社会的な階級によって人が集まる場所が歴然と分かれていることが多いのですが、日本はある面では均一性が高く、一つの空間にさまざまな人が集まります。そこに座ってじっと耳をすませていれば、自分が生活している中でなかなか交わる機会のないさまざまな人たちの情報を得ることができます。
例えば、「トラック運転手の間でこんなゲームが流行っているんだ」とわかったり、「意外にNetflixを見ている人が多そうだ」と気づいたりするのです。そして、そういった理解や気づきの積み重ねによって感性や感覚を磨くことが、自分をアップデートさせてくれます。
1日の5%は他人になったつもりで考える
もう一つ、私が自分をアップデートするために日常的にトライしているのは、性別や世代を超えていろいろな人の立場に立って考えてみることです。1日の5%ほどは、「他の人の頭」で考えているのではないかと思いますし、マーケットとも「対話」しているつもりです。
そうやって考えたことは、Facebookに投稿することもあります。例えば政治のことなら、「今の状況は岸田さんの目にはどう見えているのか、どう考えてどんな手を打つだろう」「菅さんだったら?」「高市さんだったら?」などと考えて文章に書いてみたりもします。考えるだけではなく、書いてみることで思考がより整理されるからです。
もちろん、どんなに「○○さんだったら」と考え抜いたところで、相手の心の中に入ることはできません。それでも自分の立場から離れて客観的に情勢を分析し、「この状態で○○さんだったらどうするか」と思考を巡らせることは、新たな気づきをもたらしてくれることがあります。資産運用会社の経営者という立場では、「○○証券だったらここでどう動くだろう?」などと考え、商品戦略を考えたりもするわけです。
「自分の立場を離れ、他者の立場に立って考える」ことは、先を読むための私の習慣の一つになっています。
あなたの感覚はおそらく「普通」ではない
「先の先」を読む精度を上げるためには、他者の視点を取り入れる必要があります。他者の視点を想像することは、自分自身の偏りの修正につながるからです。情報というものは、自分をアップデートする努力をサボれば、当たり前に偏りが生じるものでもありますが、そのことに気づいてさえいない人も少なくありません。
おそらく多くの人が「自分は普通だ」と思っているのではないかと思いますが、そう感じているときは注意が必要です。たいていの場合、「普通だと思っていることは普通ではない」からです。
例えば、メディアでは住宅ローンについて取り上げるときに「3000万円のローンを組んでマイホームを買う」といった設定が多く見られます。3000万円という価格は、メディアを作っているような都心に住んでいるであろう人にとっては「普通」かもしれません。
しかし、ほんの少し地方に足をのばせば、数百万円で買える広い庭付きの戸建て住宅がいくらでもあります。日本全体でみれば、3000万円のローンを組んで家を買うのが「普通」なわけではまったくありません。
同様に、男性にとって「普通」のことが女性にとっては「特殊」であったり、高齢者にとって「普通」であることが若者にとって「特殊」であったりすることもあります。もちろん、「東京に住む20代の会社員男性」のように属性が似た人であっても、二人いれば、一人が「自分は普通」と思っていることが、もう一人にとっては「普通ではない」ということだってありうるわけです。
自分をつねにアップデートしていくためには、「自分は特殊なのかもしれない」と考え、フラットにものを見られるよう、感覚を修正し続けることが欠かせません。そのような姿勢を持ち続けることができれば、「先の先」を読む土台となり、大きな失敗を減らしたり、成功する道筋を見つけたりすることにつながっていくのではないかと考えています。