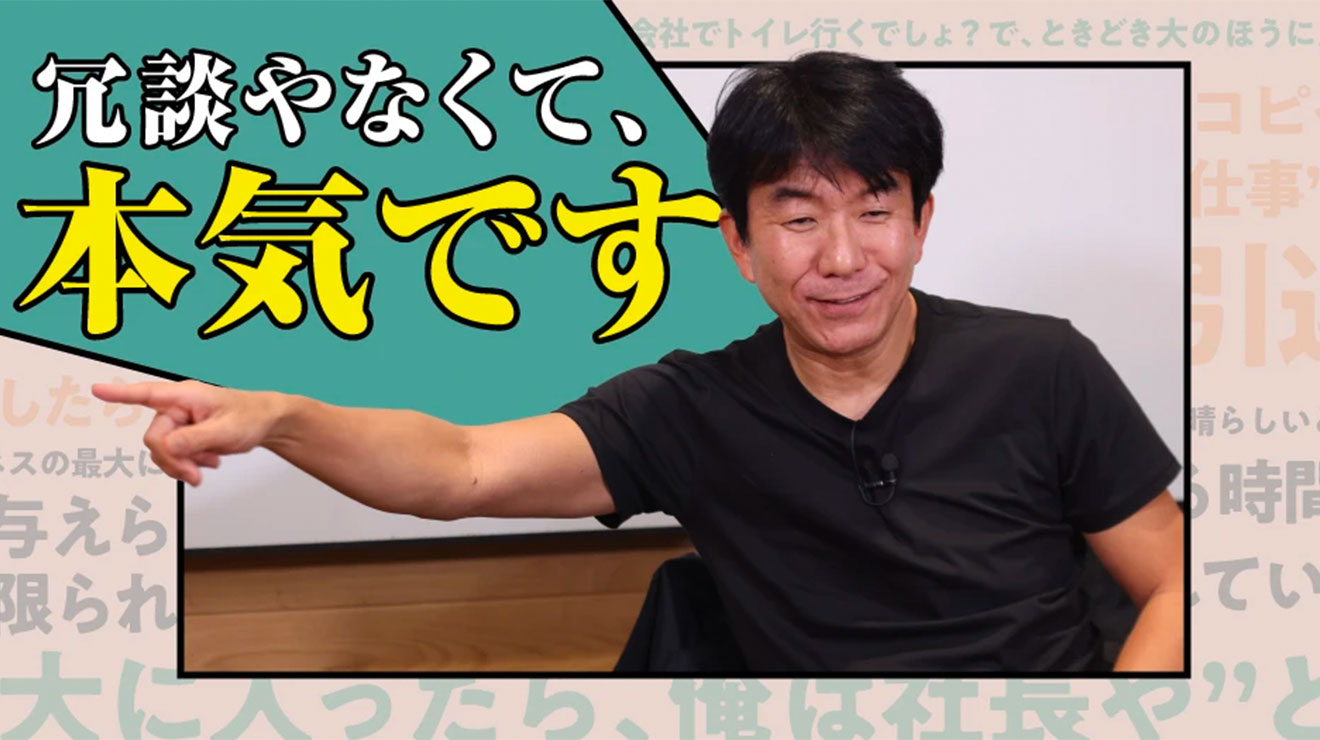濱口秀司さん。「USBメモリー」や「マイナスイオンドライヤー」など、世の中に新しい常識を生み出すプロダクトを多数企画・開発してきたビジネスデザイナーです。
現在は、某世界的リーディング・カンパニーから軍事関係まで、世界的なトップコンサルタントとして国から国へ飛び回っている濱口さん。
前編「USBメモリーの生みの親に聞く、日本が世界で勝つには」につづき、後編でお聞きしたのは「世界的コンサルタントの“3つのルール”」。
世界的に活躍するトップビジネスプレイヤーは、いったいどのような「仕事哲学」で動いているのか……?
〈聞き手=サノトモキ〉
記事提供:新R25

【濱口秀司(はまぐち・ひでし)】京都大学卒業後、松下電工(現パナソニッック)に入社。全社戦略投資案件の意思決定分析担当となる。1998 年から米国のデザインイノベーションファームZibaに参画。世界初のUSBメモリはじめ数々の画期的なコンセプトづくりをリード。パナソニック電工新事業企画部長、 パナソニック電工米国研究所上席副社長、米国ソフ トウェアベンチャーのCOOを歴任。2009年に戦略ディレクターとしてZibaにリジョイン。2013年、 Zibaのエグゼクティブフェローを務めながら、自身の実験会社「monogoto」をポートランドに立ち 上げ、ビジネスデザイン分野にフォーカスした活動 を行っている。ドイツRedDotデザイン賞審査員。イノベーション・シンキング(変革的思考法)の世界的第一人者
世界的コンサルタントは、「20代」もやっぱり驚異的だった
![]()
今日は「トップコンサルタントの仕事哲学」を教えていただきたいのですが……
そもそも濱口さんってどんな若手時代を過ごしていたんですか?
どんな経験値を積んだらこんな人材が仕上がるのか、全然イメージできないんですけど……
![]()
僕は非常にラッキーなことに、20代のころから“事業の意思決定”のサポートをしまくってたんですよ。

![]()
僕のキャリアは、“松下電工(現パナソニック)の研究職”が始まりで。
「商品企画をやりたい」と叫んでたんだけれども、学校が理科系だったから研究所に入れられてしまったんですね。
![]()
じゃあ当時はけっこう「こんなつもりじゃなかったのに」という?
![]()
意に反してましたね。企画がしたいと思って入社したのに急に「コンクリートの研究開発をやりなさい」とか言われて……
そこで「世界初のアスベストが入っていないコンクリート瓦」を開発したのが最初の仕事でした。

新卒で“世界初”を開発してしまった濱口さん
![]()
そこから結局、商品企画や研究企画もやらせてもらって、いろんな仕事を渡り歩くことができて。
で、松下電工は社内にいっぱい事業部があるんですけど、僕は“投資分析”担当として役員会議に出て、すべての事業部の重要な戦略意思決定に関わることになったんですね。
![]()
20代にしてパナソニックのあらゆる製品について将来性を分析したり判断したりしてたってことか……やば……
![]()
20代のうちからそういった“社長体験”を年に何十回と味わっていたことで、目線の高さは非常に鍛えられたかなとは思います。
そういった経験を積みながら、世界初の「マイナスイオンドライヤー」や「USBフラッシュメモリ」を発案・開発していったと……まあ、そんなキャリアですね。
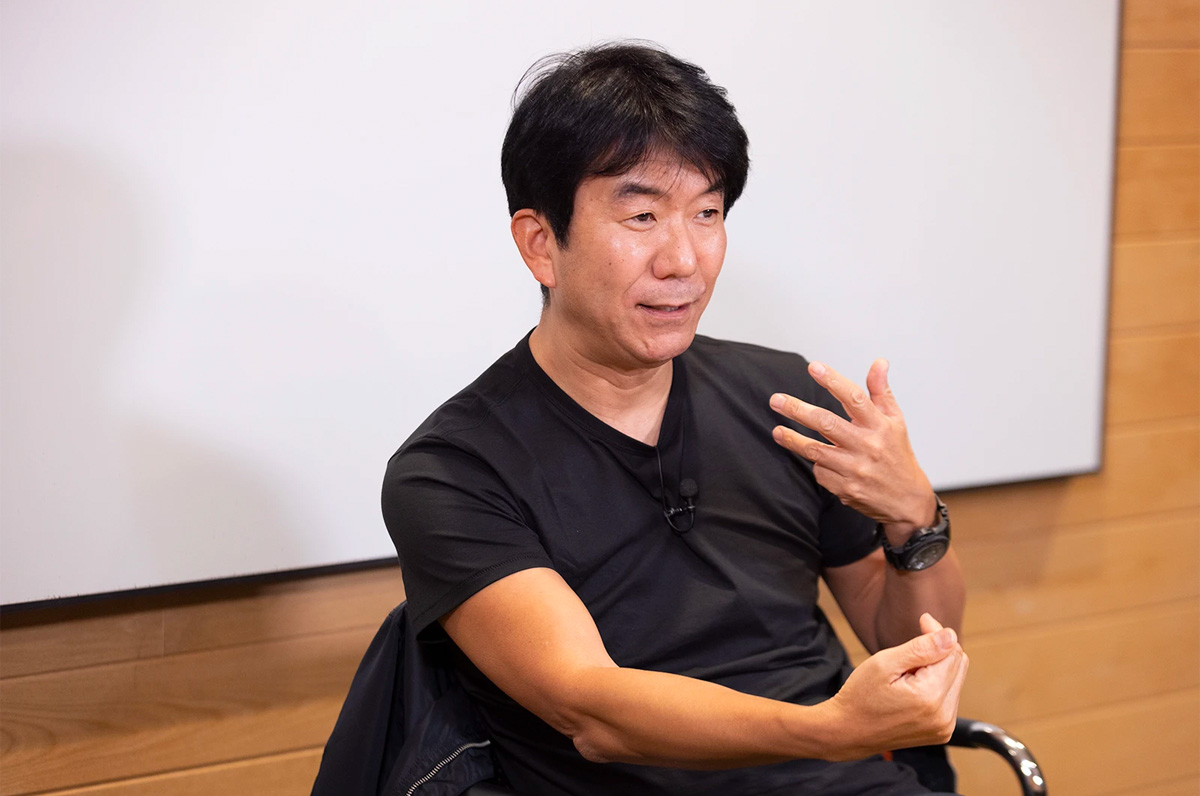
とんでもないロケットスタートだ……それではいよいよ濱口さんの「仕事哲学」に迫っていきます
濱口秀司の仕事哲学①:「トイレで“神の視点”を持つ」
![]()
濱口さんにぜひお聞きしたいと思っていたのが、「イノベーティブなアイデア」を出す秘訣で。
世界中で課題解決を任され、“世界初”のアイデアを多数実現してきた濱口さんの「アイデア哲学」を教えてください。
![]()
ひとつ言えるのは、「神の視点を持つ」ことですね。

「神の視点」……?
![]()
スティーブジョブズ、あいつがすごいのはやっぱり自分を「神」だと思っていた瞬間があったこと。
成功している企業のトップは、異口同音に言うわけですよ。「一時期、俺は神になったような気がした」。
まあ「やることやること全部当たっちゃう」みたいな勢いがないと急拡大や上場なんてしませんから、そう勘違いするのも当然なんですが。
![]()
そういうものなんですね……
![]()
さらに調子乗っちゃうのがアメリカ人で、それは強力な長所なんです。
アイデアの視点の高さが全然違ってくるんで。
やっぱり、「俺はちっぽけな存在だが、なんとかこの音楽業界に一石を投じてやるんだ……!」と考えるのと、「俺が音楽業界の未来を決める神や(ドンッ)」と構えて考えるのでは、出てくるアイデアってまるで違うんですよ。

![]()
日本人は、この「神の目線」を持つのが非常に苦手なんですよ。
なぜ、アメリカ企業のような「革命的なイノベーション」を起こせないか。それは、「視点を上げられない」という弱点が、かなり強烈なボトルネックになっているんです。調子いいときでさえ、なかなか視点を上げられない。
前回述べたコンセプトづくりにおいても、「神の目線」でフレームワーク(目的、範囲、切り口)を設計していくことが、「企画者のバイアスを破壊するアイデア」につながるわけです。
![]()
視点の高さ……たしかに弱いイメージがあるかもしれません。
でも「勝って兜の緒を締めよ」とも言いますし、好調なときこそ調子に乗ってはいけないのでは……?
![]()
そこですよ。
日本は何が何でも「調子に乗らせない」でしょう。アメリカの子どもたちの何が日本と圧倒的に違うかというと、「勘違いして育つ」ということです。
トムがバットを振ってポーン当たったら、「お前天才ちゃうか!?」「将来プロ野球選手やん!!」ってみんなで褒めまくって育てる文化。共働きが多い現代、週末はもう右から母さん左から父さんのステレオ放送で「トム! お前は天才だ!」となる。
子どものころから全員勘違いしてるんですよ。「俺天才ちゃうか?」って。

「アメリカの子どもって、ここをずーっと鍛えられている」
![]()
一方日本はどうかというと、めちゃくちゃ怒られるし減点主義。
「俺は天才だ」とか言い出したら「こいつ頭おかしいんちゃうか?」と杭を打たれて、とにかく失敗しないよう努めるようになる。
このへんの教育の違いは非常に大きいと思いますよ。
![]()
……僕も正直、めちゃくちゃまわりの目を気にして「絶対調子乗らないようにしよう」って反射的に思っちゃってる気がします。
そんなふうに育ってしまった僕でも、今から後天的に「神の視点」を養うことってできるんでしょうか?
![]()
「社長タイム」をつくってください、トイレで。
僕はそうしてます。

![]()
入社して2年で僕は気づいたんだけれども、視点というのは基本的にどんどん下がるわけですよ。
僕の同期も、入社したときはみんな「いつか社長になりたい」とか夢を語っていましたけど、半年もすれば「来週までにレポート書かなアカン」「明日プレゼンせなアカン」とどんどんスコープが小さくなって、3年たったら「社長になりたい」なんか一言も言わん。
明日の仕事・目の前のことしか目に入ってない。
![]()
ぐさぐさにぶっ刺さってます。
![]()
僕も一瞬なりかけて、思ったんですよ。「こんな目の前のことしか見えてへんヤツが、経営目線での戦略やイノベーティブなアイデアなんて出せるわけないやん」と。
“「神の視点」に引き上げる習慣”を強制的につくらんとヤバイと気づいたんですね。
そのとき考えたんが、「社長タイム」なんですよ。神よりかなりヒエラルキーは下ですけど。

詳しくお聞きしましょう
![]()
会社でトイレ行くでしょ? で、ときどき大のほうに入るでしょ?
大に入ったら、“俺は社長や”と。
「トイレの個室=視点を上げて今のアイデアを見つめ直す時間」と決めたんですよ。
![]()
世界的コンサルタントのアイデア、“トイレ”で生まれてるんですか?
![]()
そうしたら毎日強制的に、何分かは「社長タイム」が生まれるでしょう。
だから僕、プロジェクトをやってる途中、トイレ休憩から戻ってこないときがけっこうあって。
アメリカ人の同僚からテキストがくるんですよ、「濱口どこにいんねん、休憩時間終わってるぞ? クライアント待ってるぞ!」って。そのとき僕はトイレにいる。
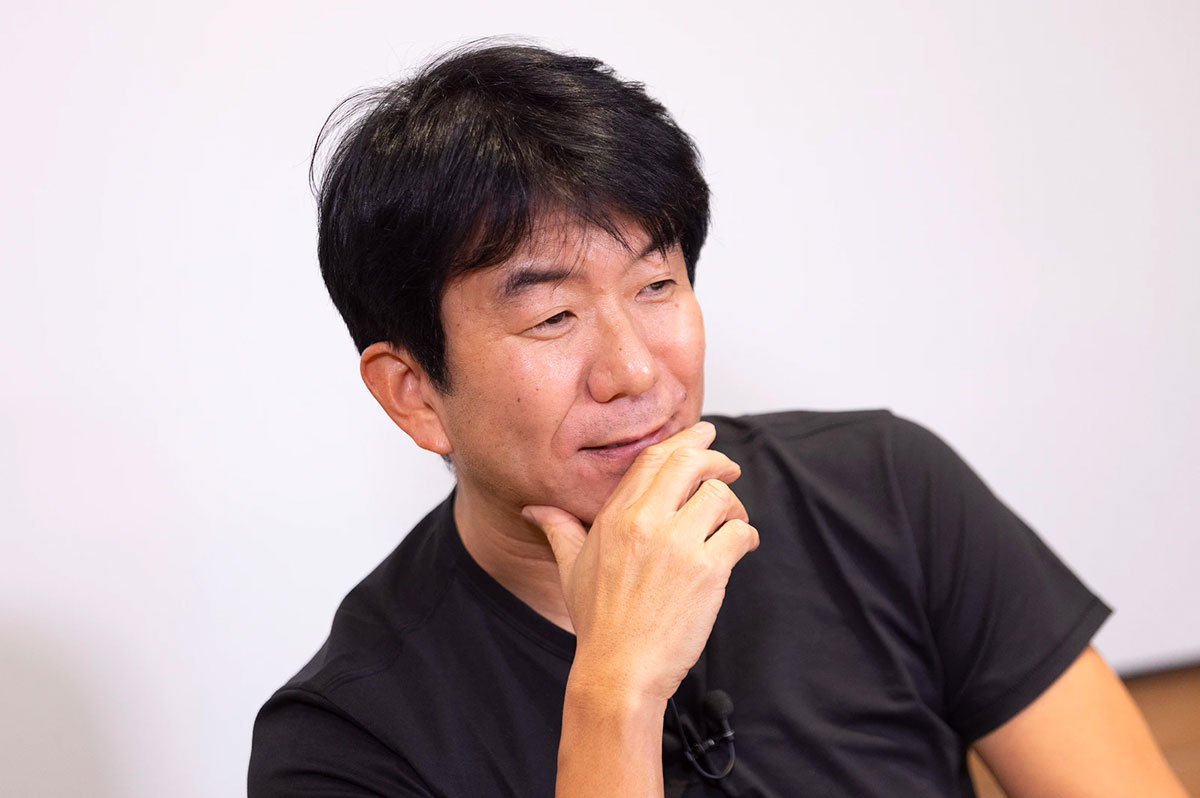
じわじわくるな
![]()
「本当にこのレベルでいいんだろうか」とトイレで考えているんですよ。
「今議論してるアイデア、本当に圧倒的に勝ちきれるサービスになっているんだろうか?」と、“社長の視点”から始まり、最後は“神の視点”まで視点を上げてアイデアを捉え直している。
おすすめですよ、トイレで「社長タイム」、「神タイム」。
![]()
ト、トイレか……(笑)。
![]()
いやこれ、冗談じゃないですよ?
人間なんてすぐ怠けるんやから、そういうことで習慣化していかなきゃいけないんですよ。
ただでさえ日本人はここが弱いんだから、習慣化してフローに組み込むくらいしないとダメです。

でもたしかに、「トイレ」という絶対的習慣に組み込むの強いかも
濱口秀司の仕事哲学②:「“コピペ仕事”をしたら、引退する」
![]()
あとね、僕、「アイデア出し」については “ふたつのルール”を決めているんです。
ひとつは、「絶対に同じ答えを出さない」ということ。
僕はどれだけ忙しくても、同じ手法は二度と取りません。
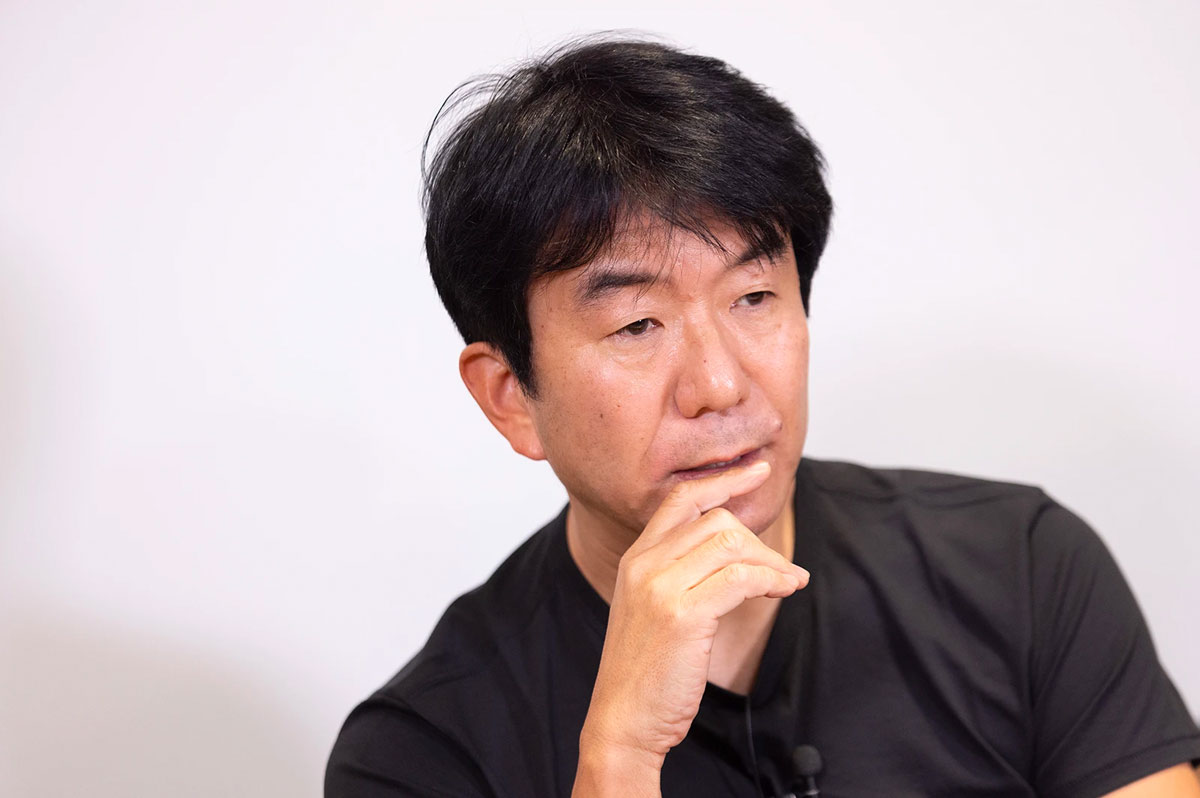
![]()
傍から見ていると、「同じ方法を繰り返してるだけで応用力はまったく高まってない人」というのはけっこういます。
頭打ちになってるのに本人は「クリエイティビティが上がってきた」と勘違いしてるケースすらあるから、まわりと差がついてから急に気づくんですよね。
![]()
……僕今28歳なんですけど、30歳を目前にその伸び悩みに直面してるかもしれません。
忙しさを言い訳に、一度成功したことのある確実なパターンに当てはめてこなしちゃうことが、正直あって。
![]()
伸び悩みを感じているなら、なおさら。どんだけ辛くても同じことはやらんことです。
「毎回ゼロから考える」。クリエイティビティはこれでむちゃくちゃ鍛えられます。

![]()
すべての仕事は一期一会。クライアントチームもクライアントの事業も自分たちの状況も競合環境も、毎回違う。同じ事業でも、2年後も同じことなんてない。
僕は過去にやったものと同じテーマのプレゼンテーションを求められたときでも、ゼロからべつのものを書きます。コピペは絶対しない。
逆に、“コピペ”で仕事をしたくなったらもう終わり。「自分のクリエイティビティはもうなくなっている」と判断して、引退しようとルールを決めてます。
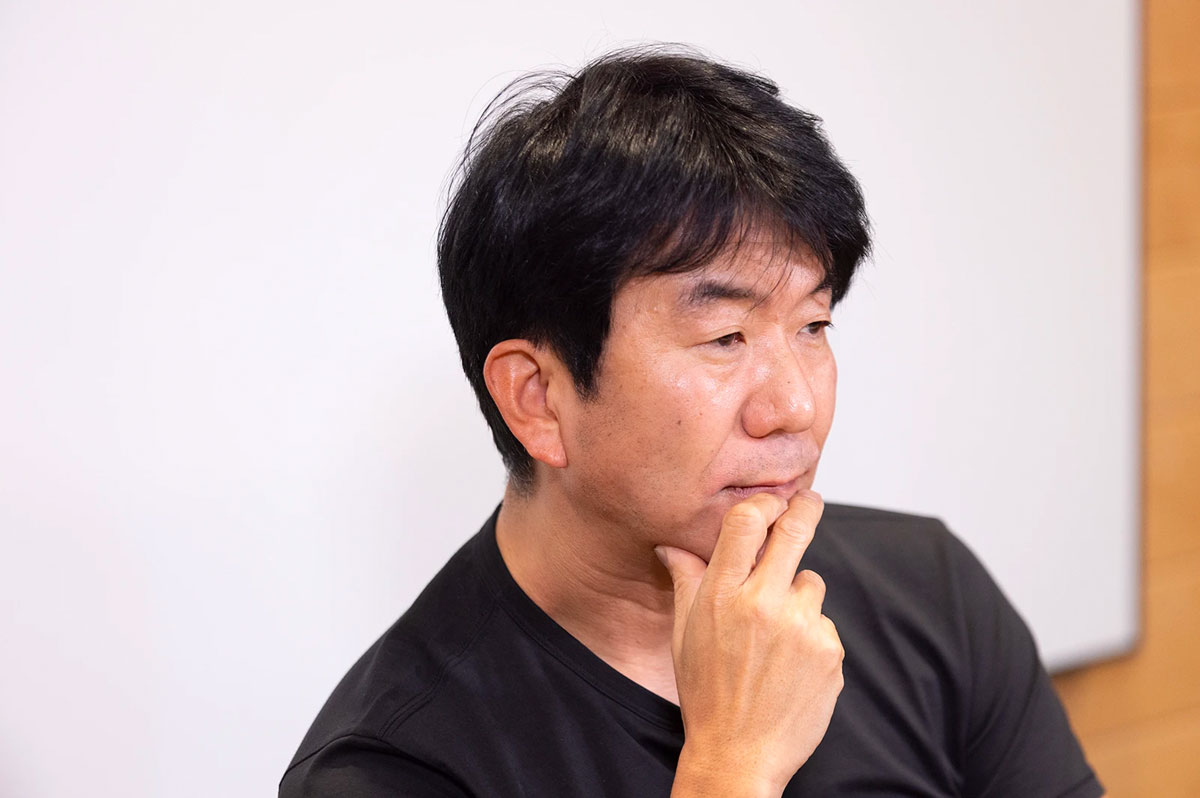
これが“トップ”の覚悟
濱口秀司の仕事哲学③:「クオリティではなく“時間”で進める」
![]()
そして、アイデア出しのもうひとつのルールは……
「あらゆる思考プロセスは“時間”で切る」というもの。

![]()
ビジネスをしていると、「どこまでいったらGOを出すか」という議論がありますよね。
このとき、絶対に「クオリティ」じゃなく「時間」で区切ってください。
あらゆる思考プロセスは、定性じゃなく“定量”で管理すべきです。
![]()
質的管理じゃなく、「量的管理」……
量的管理というと、具体的にどのような区切り方になるのでしょうか?
![]()
「アイデアを30分、ロジックを30分で考える」みたいに時間で切るのもいいし、「アイデアはノートの左側1ページ、ロジックは右側1ページで考え切る」みたいに物量で切るのもいい。
その範囲で考え切ったら、それがどんなクオリティであっても「さ、アクションや」です。

![]()
でも、本当にそれでいいんでしょうか。
前回の記事で、「イノベーションを起こすには、いかに“コンセプトづくり”にリソースをさくかが重要」というお話もされてたと思うんですが……
時間を理由に、クオリティを妥協して前に進めるべきではないのでは?
![]()
妥協でもなんでもない。それが“ビジネス”です。
完璧な事業戦略を、設立から75年考えつづけて完成させたってダメなわけです。与えられた時間のなかで、ベストじゃなくても動きはじめないといけない。
“日本企業の問題は「コンセプト設計フェーズ:実行フェーズ=1:10000」のバランスでリソースを割くべきところを、コンセプトに「0.001」しかかけていないこと”……と前回言いましたが、目指すべきは所詮「1」なわけで、すぐ到達できるんです。
最善じゃなくても真理じゃなくてもいい。「時間内に出たより良いアイデアでやればいい」というのがビジネスの本質です。
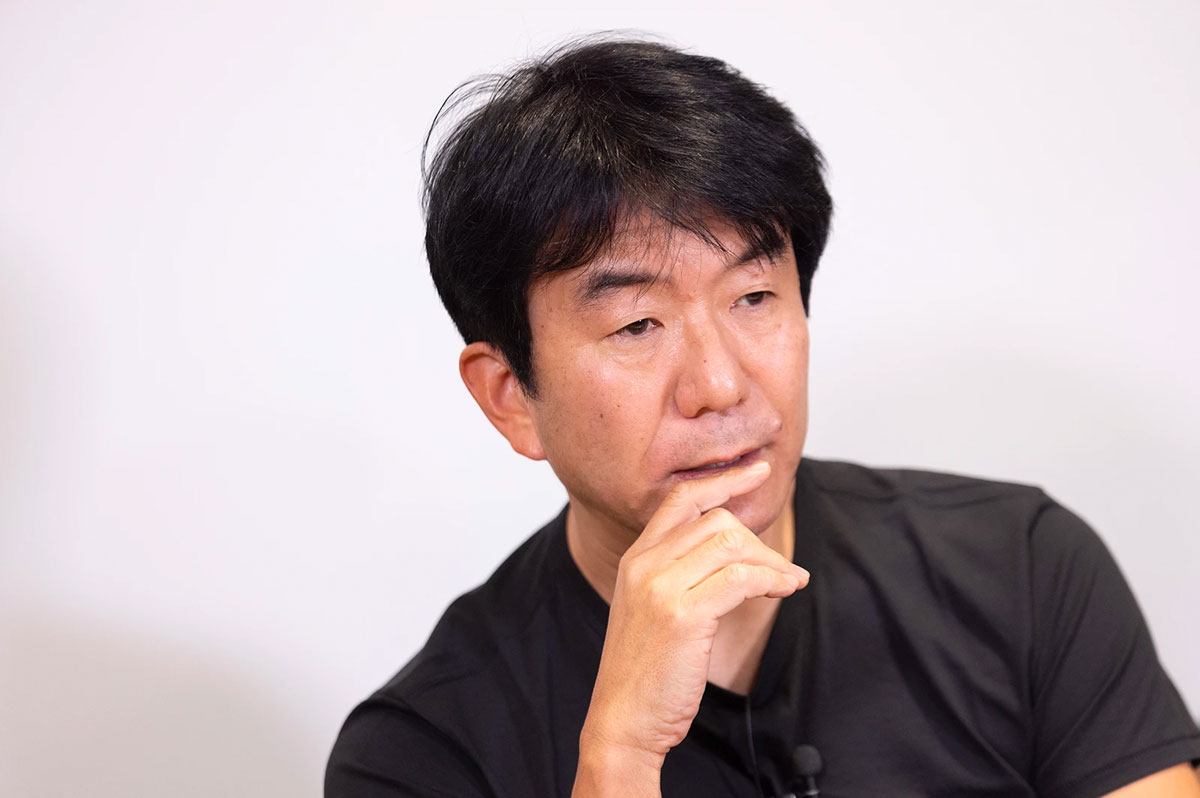
![]()
ビジネスの最大に素晴らしいところは、「与えられる時間が限られていること」。
もし僕らがサイエンス(研究)の世界の人間なら、このアイデアこそが「真理」であると説明できなきゃいけない。あの世界には「たったひとつの正解」を追いかけて気が狂う人もいるわけです。
でもビジネスで求められるのは、答えを見つけることじゃなく「結果を出すこと」ですから。
![]()
……!
![]()
考えて、やってみて、変なことが起きたら対応する。この繰り返しでいいんですよ。
正解を探しだした時点で崩壊するし、「このアイデアどう思います?」と聞かれても、正直うまくいくかなんて本当のところは僕にもわからへん。やってみるまで、誰にもわからんのです。
ビジネスは人間がやってることだから、不確実性いっぱいあるし、どんだけ考えたところで思った通りになんてならんのです。「計画通り」なんて言うてんのはデスノートの夜神月だけ。
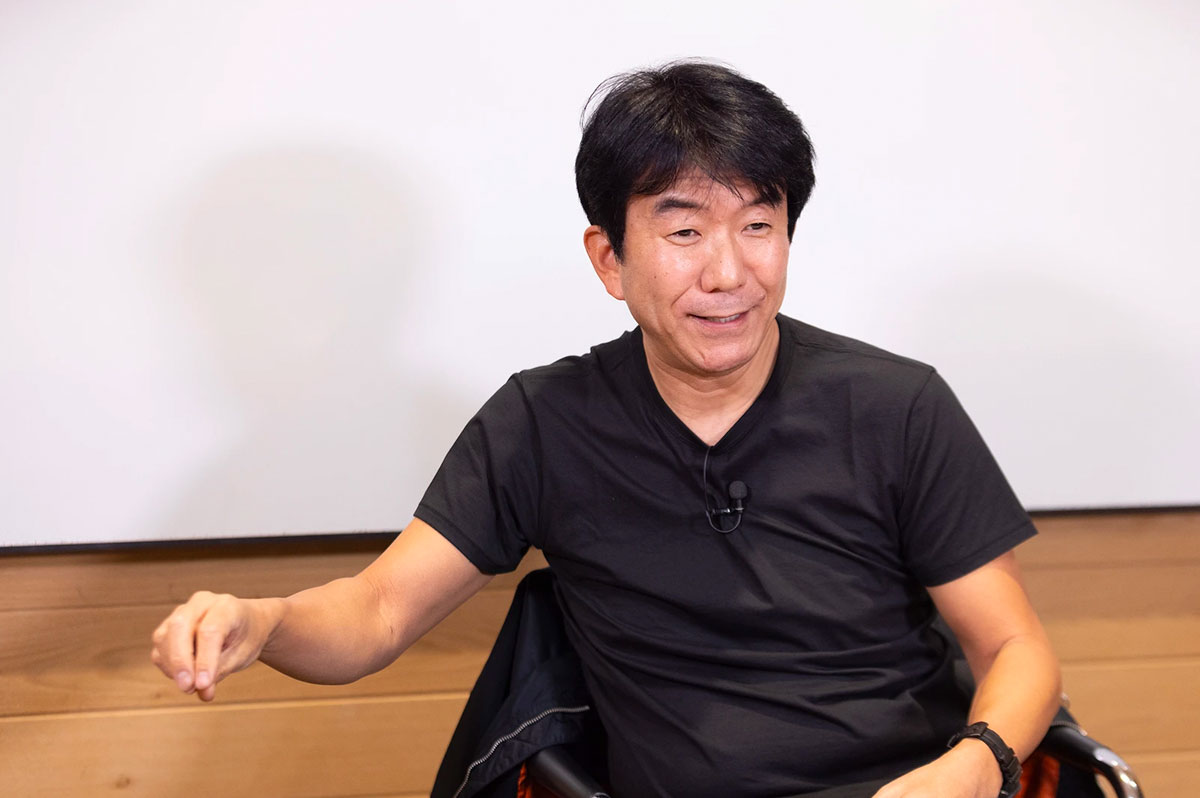
突如新R25に駆り出される夜神月
![]()
ここを勘違いして“クオリティ”で物事を決断している人が……判定しようのない“クオリティ”を追求して時間を無駄にしている人がいっぱいいる。
アイデアにはキリがない。考えようと思えば一生考えつづけられますから。
「クオリティが良くなったら前に進む」ってやった時点で、基本的にプロジェクトは崩壊します。
![]()
「クオリティを基準にビジネスを進めるな」……濱口さんに言われると説得力がすごい。
「まだ穴がある」とわかっていても、走り出したほうがいいということですよね?
![]()
それでも走り出してください。構造的にどこが考えきれていないかわかりながら走ってれば問題ないです。
「ほかのアイデアよりはベターだろう」で次に移っていいのが、ビジネスです。
判断に悩んだら思い出してください。「僕らがやってるのはサイエンスじゃなく、ビジネスである」と。

あまりにも痺れる締め。本日は本当にありがとうございました!
「日本の勝ち筋」を聞いた前編とはうってかわって、濱口さんの個人的な「仕事哲学」に迫った今回の取材。
小手先のテクニックやノウハウのお話は一切なし。仕事人として持つべき「美学」の連続で圧倒されました。
筆者、取材を聞き、書籍(論文集)を買い、濱口さんにお聞きしたいことが取材前の3倍くらいに増えてしまいました。いつかまた濱口さんに対峙し続編をお届けできるよう、自分を成長させて戻ってきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!
〈取材・文=サノトモキ(@mlby_sns)/編集=福田啄也(@fkd1111)/撮影=長谷英史(@hasehidephoto)〉