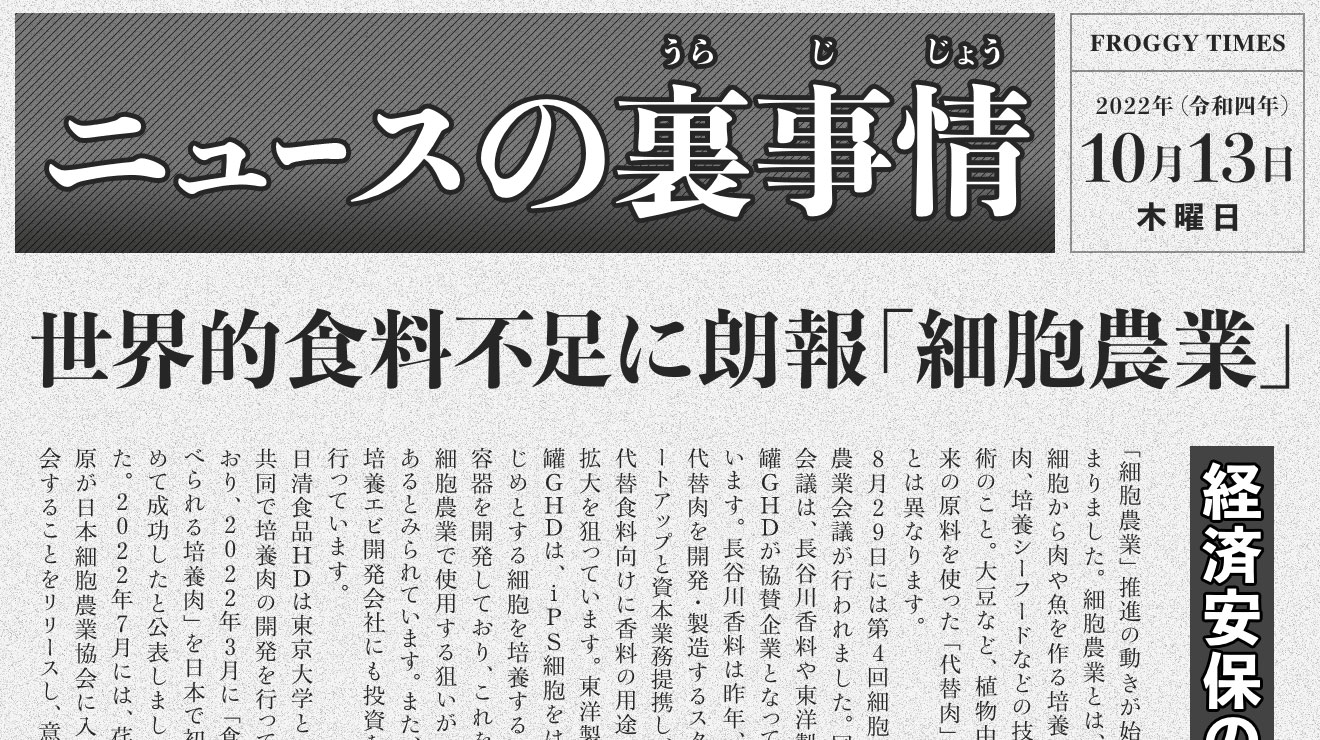テレビや新聞で取り上げられたニュースの裏側を解説する本連載「ニュースの裏事情」。今回は、世界的な食料不足から注目される「細胞農業」に関するニュースの裏側についてご紹介します。
経済安保の一環で政府も推進へ
「細胞農業」推進の動きが始まりました。細胞農業とは、細胞から肉や魚を作る培養肉、培養シーフードなどの技術のこと。大豆など、植物由来の原料を使った「代替肉」とは異なります。
8月29日には第4回細胞農業会議が行われました。同会議は、「 長谷川香料 」や「 東洋製罐GHD 」が協賛企業となっています。長谷川香料は昨年、代替肉を開発・製造するスタートアップと資本業務提携し、代替食料向けに香料の用途拡大を狙っています。東洋製罐GHDは、iPS細胞をはじめとする細胞を培養する容器を開発しており、これを細胞農業で使用する狙いがあるとみられています。また、培養エビ開発会社にも投資を行っています。
「 日清食品HD 」は東京大学と共同で培養肉の開発を行っており、2022年3月に「食べられる培養肉」を日本で初めて成功したと公表しました。2022年7月には、「 荏原 」が日本細胞農業協会に入会することをリリースし、意欲を示しています。
細胞農業が注目されているのは、今後世界的に食料不足が想定されているからです。細胞農業は家畜の飼育が不要で、魚の乱獲も防ぐことができます。さらに、牛がゲップすることによって放出されるメタン(温室効果ガスの一種)の排出量も抑えられ、カーボンニュートラルにも貢献します。
動物の命を奪うわけではないので、菜食主義者も食べられるようになり、需要拡大も期待できます。ただ、現状は培養肉を作るためのコストが「ハム1枚に15万円」と高価なため、いかにコストを抑えるかが課題となっています。
2022年6月には「細胞農業によるサステナブル社会推進議員連盟」が設立されました。背景には「食料安保は経済安保につながる。ロシアのウクライナ侵攻で穀物は高騰し、肥料はひっ迫。日本人の栄養確保を維持するために、細胞農業は有効だ」(自民党国会議員)という考え方があるようです。
細胞農業は、バイオ系の学者はもちろん、「多摩大学ルール形成戦略研究所」も推進しています。同研究所は國分俊史多摩大学大学院教授が所長を務め、自民党の甘利明前幹事長と二人三脚で政府の経済安全保障政策をリードしてきました。6月に設立された議員連盟でも、甘利氏が総会で冒頭挨拶を行っています。政府は経済安保の一環で細胞農業を推進するとみられています。
安保絡みとなれば、政府の対応は力が入ります。その点からも、細胞農業には注目が集まりそうです。
(出典:日本証券新聞)