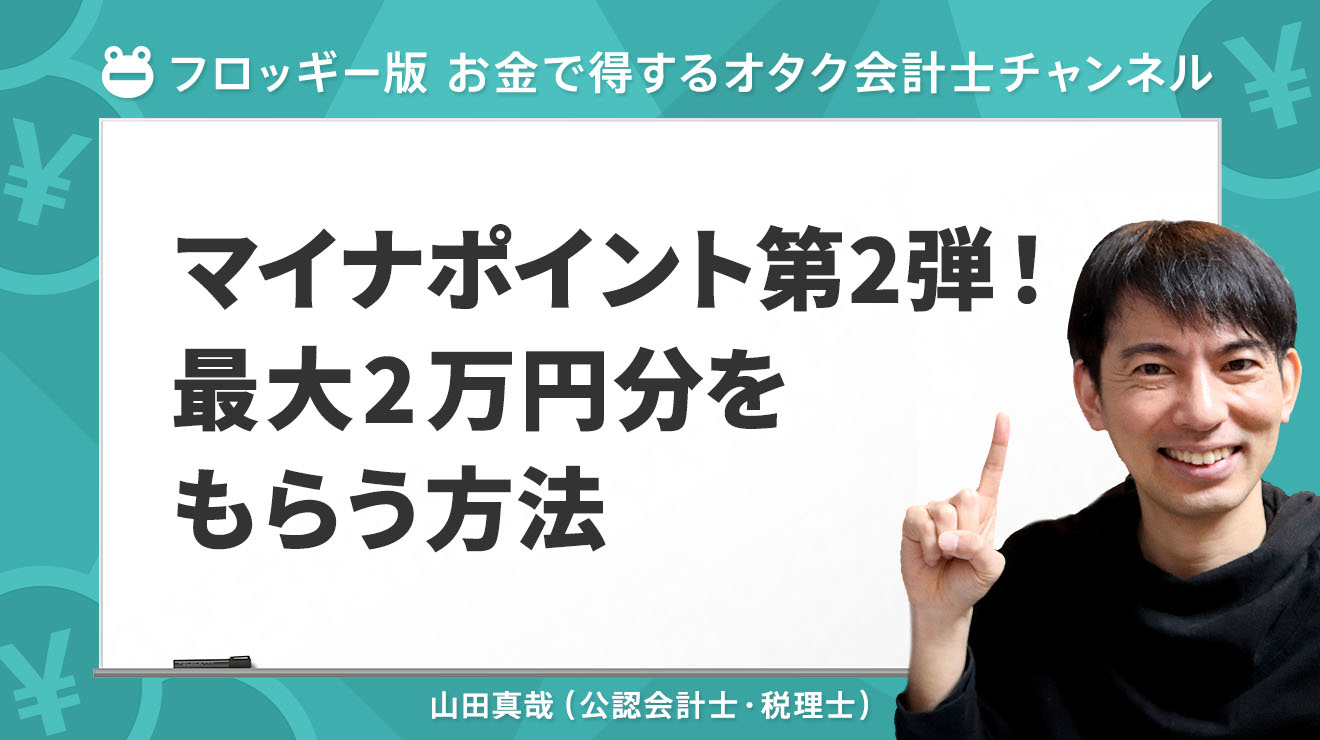みなさんこんにちは! 公認会計士・税理士の山田真哉です。先日auショップに行ったら、マイナポイントのパンフレットをいただきました。賛否両論あるマイナポイント事業ですが、今回は、現在行われている「マイナポイント第2弾」について、お話したいと思います。
第1弾で申請しそびれた人もチャンス!
はじめに、マイナポイント事業について、簡単におさらいしましょう。
まず、2020年9月から2021年12月にかけて「マイナポイント第1弾」が行われていました。これは、マイナンバーカードを作り、自分で選んだキャッシュレス決済サービスでチャージや買い物をすると、最大5000円分のポイントがもらえるという事業でした。何のポイントがもらえるかというと、PayPayやSuicaといった、ご自身で選んだキャッシュレス決済サービスのポイントです。
そして、現在行われているのが「マイナポイント第2弾」です。こちらは、2022年1月から2023年2月までの期間限定で、最大2万円分のポイントがもらえる事業です。まず、第1弾に申し込んでいない人は、なんと、今回申請すれば最大5000円分のポイントがもらえます。それからマイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みと、公金受取口座の登録で、さらに1万5000円分のポイントがもらえます。
つまり、最大2万円というのは、第1弾の5000円分のポイントをもらっていなかった人は、5000円+1万5000円で合計2万円という意味合いです。ですから、第1弾の時に5000円分もらっている人は、今回は最大1万5000円分がもらえる、ということになります。
「マイナポイント第2弾」とは
では、「マイナポイント第2弾」について見ていきましょう。ざっくり言うと、4つのステップがあります。
②マイナポイントの申込みとキャッシュレス決済サービスの選択
③2万円分のチャージor買い物で5000円分GET
④健康保険証の利用申込み、公金受取口座の登録で1万5000円分GET(2022年6月30日(木)開始)
すでに「マイナポイント第1弾」に参加した人は、「マイナポイント第2弾」では、6月30日から始まる④のみ参加可能です。今回は、マイナンバーカードを手に入れていなくて、第1弾にも参加していない場合の手続き方法から、お話しします。
ステップ①
まずは、マイナンバーカードの申込用紙を取り寄せて、お住まいの市区町村の役所に申込み手続きをしましょう。ちなみに、私がauショップでもらったパンフレットには、マイナンバーカードの申込用紙が入っていました(ちゃんと封筒もついていました)。ほかにも、ネットから申込用紙をダウンロードすることもできます。この申込用紙を役所に送ると、1ヵ月後くらいに役所から呼び出しがあります。そこで手続きをすると、数週間後にマイナンバーカードが手に入ります。
ここで注意していただきたいのが、マイナンバーカードの取得期限は2022年9月末ということです。おそらく9月までにマイナンバーカードの申込みをしないと、取得期限に間に合わず、マイナポイント第2弾に参加できなくなります。現状、マイナンバーカードの普及率は4割程度らしいので、ポイントが欲しいという方は、早く申し込んだ方が良いと思います。
ステップ②
マイナンバーカードを手に入れたら、スマホなどを使ってマイナポイントの申込みとキャッシュレス決済サービスの選択をします。このとき、大手の決済サービスを使って手続きをすると、マイナポイントの申込みとキャッシュレス決済サービスの選択が同時にできます。たとえば、僕が使っているLINE Payは、マイナポイントのボタンがあるので、そこから手続きに進むことができます。
ステップ③
ステップ②が完了したら、選んだキャッシュレス決済サービスでチャージ、もしくは買い物をするとポイントがもらえます。ポイントの還元率は25%(上限5000円分)なので、2万円分のチャージor買い物をすれば、5000円分ポイントがもらえます。なお、ポイントがもらえるタイミングは、選んだキャッシュレス決済サービスによって異なります。
ステップ④
2022年6月30日からは、マイナンバーカードを健康保険証の代わりにする、通称「マイナ保険証」の利用申込みと、公金受取口座の登録もマイナポイントの対象になります。すでに保険証の申込みや口座登録が済んでいる、という方も、申請すればポイントがもらえます。
具体的には、スマホにマイナポータルのアプリを入れて、そこで操作をすることになります。申込み、登録が完了したら、6月30日以降にマイナポイントの申請ができます(申請期限は2023年の2月まで)。マイナ保険証を申し込むと7500円分のポイント、公金受取口座の登録をすると7500円分のポイントがもらえます。両方手続きすれば、合計1万5000ポイントがもらえる、というわけです。もちろん、どちらかだけを選択して7500円分のポイントを得ることも可能です。
公金受取口座を登録するメリット
ちなみに、公金の受取って、年金の受け取りのイメージがあったりしませんか? とくに若い人は、口座を登録する必要はないんじゃないかと思うかもしれません。でも、たとえば子どもが生まれたら、児童手当を受け取る口座になります。あるいは、確定申告をしてふるさと納税(寄附金控除)や医療費控除を受ける方は、所得税の還付金を受け取る口座にもなります。
なので、確定申告などでいちいち還付金の口座を書かなくて済む、というメリットはあると思います。さらに、新型コロナウイルスに感染して給付金を受け取る場合も、口座を登録しておけば、すぐに受け取れるよ、という意味合いの口座になります。
国に銀行口座を知られたくない、と思う方もいらっしゃるかも知れませんが、そもそも所得税の還付金をもらう時には口座情報を書かないといけませんし、税務署が本気を出せば、国民の口座は全部バレてしまいます。
とはいえ、心配な方は、新しく銀行口座を作って、その口座を登録するというのもアリだと思います。
スマホで手続きできない場合は?
マイナポイントはスマホで手続きできますが、スマホを持っていなかったり、操作に慣れていないといった場合は「マイナポイント手続きスポット」でも手続きができます。役所の窓口や、携帯ショップなどが手続きスポットになっています。最初にauショップでパンフレットをもらったと言いましたけど、なんでもらったかというと、auショップ自体がマイナポイント手続きスポットだからなんですね。
また、家族のスマホを使って手続きしてもOKです。15歳未満の場合は、公的に親が代理申請できます。18歳未満の場合は、親の決済サービスを使って、ポイントを貯めても問題ありません。ただ、決済サービスは変えないといけないので、自分の分はPayPayで、子どもの分はau PAYで、のように分ける必要があります。
あとはパソコンでも手続きできます。ただ、パソコンの場合はマイナンバーカードを読み取るカードリーダーが必要なので、注意が必要です。
実際の手続き方法は動画もチェック!
というわけで、今回は「マイナポイント第2弾」についてお話しました。事務的な手続きで面倒に思ってしまいがちですが、所得や年齢に関わらず、申請すれば誰でもポイントがもらえるという制度は、あんまりないと思います。申請期間は限られているので、この機会にぜひ最大2万円分GETしていただければと思います。実際の手続きは、僕のYouTubeでもご紹介していますので、気になった方はご参照ください!
それでは、またお会いしましょう! ば~いば~い!