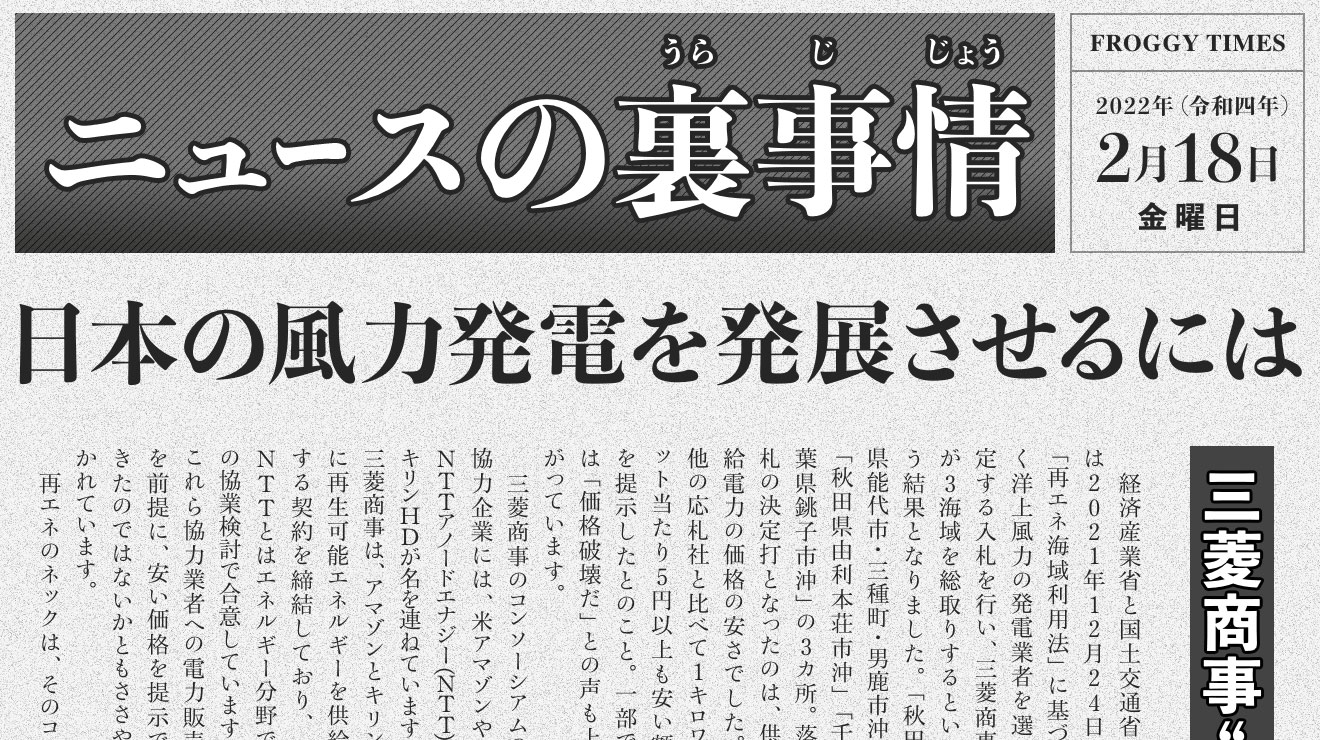テレビや新聞で取り上げられたニュースの裏側を解説する本連載「ニュースの裏事情」。今回は、日本の風力発電事業に関するニュースの裏側についてご紹介します。
三菱商事“一人勝ち”の背景とは
経済産業省と国土交通省は2021年12月24日、「再エネ海域利用法」に基づく洋上風力の発電業者を選定する入札を行い、「 三菱商事 」が3海域を総取りするという結果となりました。具体的には「秋田県能代市・三種町・男鹿市沖」「秋田県由利本荘市沖」「千葉県銚子市沖」の3ヵ所です。落札の決定打となったのは、供給電力の価格の安さでした。他の応札社と比べて1キロワット当たり5円以上も安い額を提示したとのこと。一部では「価格破壊だ」との声も上がっています。
三菱商事のコンソーシアム(共同企業体)の協力企業には、米アマゾンやNTTアノードエナジー( NTT )、「 キリンHD 」が名を連ねています。三菱商事は、アマゾンとキリンに再生可能エネルギーを供給する契約を締結しており、NTTとはエネルギー分野での協業検討で合意しています。これら協力業者への電力販売を前提に、安い価格を提示できたのではないかともささやかれています。
他社にチャンスはあるか
再エネ(再生可能エネルギー)のネックは、そのコストの高さにあります。割高な電力は普及が難しく、今回の「価格破壊」は、カーボンニュートラルを推進する政府にとって朗報とも言えます。しかし、早くも業界から批判の声が上がっていると言います。
「つまりは、三菱商事の価格には勝てないということです。三菱商事以外の事業者が落札できなくなると、日本の風力発電産業が潰れてしまうので、今後の入札では最低価格を設け、ほかの応札社にもチャンスを与えるべきだという意見も出ている」(経産省担当記者)
実際、今回の入札で有力視されていた「 レノバ 」は受注できなかったことで、株価が暴落するという騒動もありました。
今回の入札を疑問視する意見も出ています。京都大学大学院の山家公雄特任教授は三菱商事の受注に対して、「事業化・産業化の実現性に疑義あり」とした論文をまとめ、ネットに掲載。「驚愕の低価格は『リスクを低く想定』と『楽観的な事業見通し』によるものと推察する」とも書かれています。
1月27日の自民党再生可能エネルギー普及拡大議連に山家教授が招かれ、ヒアリングに応じています。今回の入札は政治絡みになってきました。萩生田経産相も1月7日の大臣会見で今回の入札について「(三菱商事以外の)ほかのプロジェクトの人たちにも今後参加しやすいような仕組みを、ぜひ今回の結果を踏まえていろいろ検討してみようかなと思っている」と述べていました。
国は洋上風力の調整を進めており、今後は残る18海域の入札に注目が集まりそうです。
(出典:日本証券新聞)