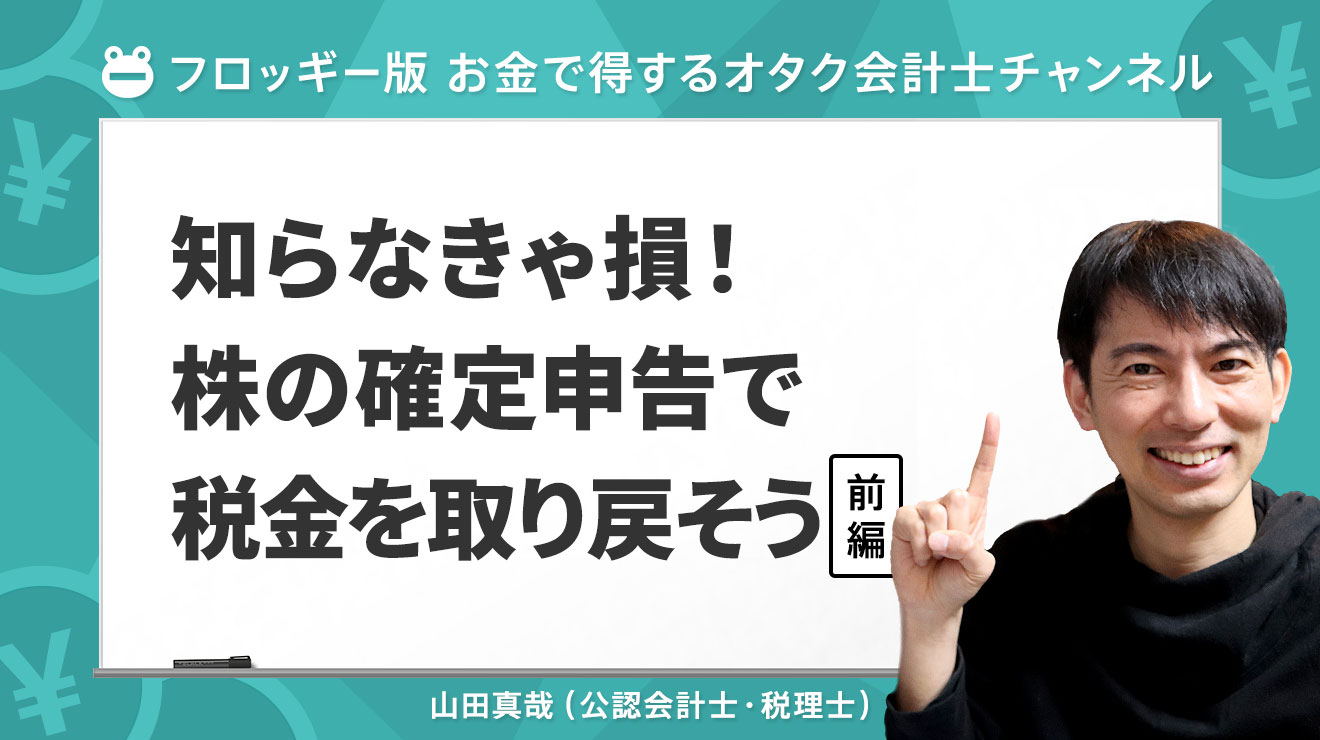みなさんこんにちは! 公認会計士、税理士の山田真哉です。
今回は、株や投資信託の確定申告についてお話ししたいと思います。
まず、今回の話で私が対象としているのは、以下の両方に当てはまる方です。
・上場株式投資や投資信託の運用をしている方
(※NISAやiDeCoは、もともと非課税で税金がかからないので、今回は対象外です)
確定申告の前に知っておきたい3つのこと
株や投資信託の確定申告のお話をするにあたって、是非知っておいてほしいことが3つあります。
②「源泉徴収ありの特定口座」かつ「株式数比例配分方式」にしていれば確定申告は不要
③税金の手続きは証券会社が代行してくれる
株や投資信託を保有している場合、配当金や分配金、売却益といった利益には、税金がかかります(※NISA口座を除く)。配当金や分配金が出ない場合は、売却しない限り税金は発生しません。さらに、売っても利益が出なければ、税金はそもそもかかりません。
株や投資信託の税金は「分離課税」と呼ばれますが、税金の内訳は、所得税が15.315%、住民税が5%で、合計すると20.315%の税率になります。
「分離課税」の反対語は「総合課税」です。総合課税は、毎月会社からもらうお給料などが対象で、所得に応じて税率が変わります(所得税と住民税の合計で15%~55%かかってきます)。
ここで気づいた方もいるかもしれませんが、株や投資信託は、いくら利益が出ても税率は20.315%のままなんです。これって、すごくないですか……!? 普段、給与所得などで40~50%税金を払っているような高額所得者の方でも、株や投資信託に関しては20.315%で良い、と言ってくれているわけなんですね。
なぜお金持ちを優遇するんだ! と思うかもしれませんが、逆の立場になって考えると、配当金や売却益が入ってきても、常に40〜50%税金で引かれてしまうなら、わざわざリスクを取って運用するのがバカバカしくなりますよね。
そうして運用する人が減ると、それはそれで日本経済も困ってしまうので、高額所得者の方も安心して株をやってください、という意味合いもあって、株や投資信託に関しては、他の収入と分離して課税します、その税率は20.315%ですよ、としているわけなんですね(令和4年の税制改正で、この20.315%という税率を見直すかも? という話がありましたが、一旦見送りになりました)。
それから、税金が発生した時に「源泉徴収ありの特定口座」かつ「株式数比例配分方式」という届出をしていると、証券会社が税金の手続きを代行してくれるので、確定申告が不要になります。「株式数比例配分方式」は、ややこしい名称になっていますが、ようは配当金の受け取りを証券会社の口座にするという方式です。
この届出をしておくと、配当金や分配金、売却益などは自分の証券口座に入ってきます。
そのとき、税金はどうなるかというと、じつは証券会社が配当金や売却益の一部を「源泉徴収」という形で引いて、それを既に税務署に納めてくれているんです。
証券会社から送られてくる書類を見ると分かりますが、実際に所得税がいくら、地方税(住民税のことですね)がいくら、と書かれていると思います。なので厳密には、源泉徴収済みの金額が自分の証券口座に入金されるということですね。
というわけで、「源泉徴収ありの特定口座」かつ「株式数比例配分方式」にしておけば、確定申告は不要でOKです。当然不要なだけであって、確定申告をしても良いということです。仮に税金を払い過ぎているとしたら確定申告をすれば良いし、そうでなければ何もしなくて良い、ということですね。
なお「源泉徴収なしの特定口座」、あるいは「一般口座(これは源泉徴収なしになります)」の場合は、証券会社が代行してくれないので確定申告が必要です。自分は一般人だから一般口座を選ぼうと思ってしまうかもしれませんが、それは関係ありません。「一般」というのは「何もしてくれない」という意味です。
利益と損失の合算で税金が戻ってくる!
「源泉徴収ありの特定口座」で「株式数比例配分方式」にしておくと、証券会社が勝手に税金を納付してくれるっていうのが良いところなんですが、じつはそれだけじゃないんです。
それはズバリ、証券会社が勝手に「損益通算」というものをやってくれるところです!
ちょっとややこしいので、いくつか例を挙げてみましょう。
たとえば、1年間(税金は1月から12月で計算します)のトータルの売却益が15万円、売却損が10万円出たとしましょう。そうすると証券会社の方で、利益と損失を計算して、差し引きの利益を5万円にしてくれるんです。
その5万円に税率20.315%をかけて、10,157円の税金を払いましょう、というのを証券会社の方でやってくれるんですね。これが「損益通算」です。
この場合も、売却損と配当金を計算して、差し引きの利益は2万円になります。その2万円に対して税金を払うことになります。
この場合は、差し引きすると損失が45万円になりますね。配当金5万円だけだったら、税率20.315%をかけて、10,157円の税金がかかるはずなんですけど、配当金よりも損失が多いので、この10,157円の税金は、自動的にもとに戻されます。最終的に売却損と相殺されるわけですね。
じゃあ、残りの損失45万円分は、他の所得、いわゆる給与所得や事業所得、一時所得、不動産所得といった他の所得と合算して、損益通算できるのかというと……それはできません(汗)。
でも、利益を出した時だけ税金をとって、損した時は何もしないっていうのは、ちょっと平等主義的にいかがなものか、というのがありまして、売却損が出たときには、なんと将来的に税金が還付されるかもしれないっていう制度があるんです。
3年以内なら、税金が戻るチャンス
それが「3年間の譲渡損失の繰越控除」という制度です。損失が発生したら、それを翌年と翌々年に、合計で3年間繰り延べることができるんです。使わなかった携帯のギガを翌月に繰り越すみたいなイメージですね。
この制度を利用するには毎年確定申告が必要で、仮に来年、再来年全く取引しなかったとしても確定申告をし続ける必要があるんですが、それでも非常にお得な制度だと思います。
具体例を挙げてみましょう。
この場合、証券会社は自動的に令和6年の売却益35万円に対して税率20.315%をかけて、71,102円の税金を納める手続きをします。ところが、令和4年、5年と確定申告をして、そして令和6年に確定申告をもう一度すれば、先に納税の手続きをされていた71,102円の税金が還付されるんです。
つまり、将来の利益と相殺しますよ、というのが「譲渡損失の繰越控除」という仕組みなんですね。「損失が出たら、まずは確定申告をしよう」ということだけでも覚えておくと良いと思います。
ちなみに、令和3年に売却損が45万円、令和6年に35万円の利益が出て相殺すると、10万円分の損失が残りますよね。この10万円はどうなるかと言うと、もう3年経ってしまったので、4年目以降はドボンです。令和7年には繰り越せず、10万円は損失のまま終わったね、ということになります。
なので、売却時に損失が出そうなときは、その後3年以内に売却益が出せるかどうかも考えて売買できると良いと思います。
配当金の確定申告にも注目
今回は「損失の繰り越し」で税金を取り戻す方法をご紹介しましたが、税金の還付を受けるために確定申告をした方が良いのは、損失が出たときだけではありません。じつは配当金を沢山もらった! という時も、ぜひ確定申告をしていただきたいです。次回は、その方法について、見ていきたいと思います。
それでは、またお会いしましょう! ば~いば~い!