販売実績世界一でギネス認定された『お〜いお茶』。文字通り、日本の緑茶市場をけん引してきた同ブランドだが「海外を含め無糖市場の広がりを考えても可能性はまだこれからだ」という。ブームの“濁り”茶に参入しない理由や匠の技そのものである味づくりへのこだわりまで、伊藤園マーケティング本部の安田哲也さんに語ってもらった。
名称変更で売上6倍!『お〜いお茶』の誕生秘話【前編】を読む
『お~いお茶』はホットとコールドで味づくりが違います
容器やサイズを手がかりに、お客様の飲用シーンを細かく設定しているんです。
たとえば、ホット用とコールド用では原料として使用する茶葉はまったく違います。ホット用は温かくして飲みますよね。温かいお茶は冷たい時よりも味や香りを弱く感じます。また、寒いときほど濃いめの味が求められます。
お客様がホットを飲むシーンを描きながら、どのような味や香りが良いか開発部門と意見をすり合わせながら品質を仕上げていきます。

伊藤園マーケティング本部・緑茶ブランドグループブランドマネジャーの安田哲也さん
1本飲みきったときに満足いただける味わいになるように、ぞれぞれの容器容量に合わせて味づくりをしています。例えば「じっくり味わって飲むのは“飲みきりサイズ”の方だよね」という考え方です。
これが2Lサイズなら「ごくごく飲む」シチュエーションのほか、お客様にお出しするなど「氷をいれて飲む」可能性もあります。このように飲用シーンを考えながら最良の味わいをつくりあげていきます。
また、これらのベースになるのが「春夏に飲むか」「秋冬に飲むか」。
『お~いお茶』は年に2回ほど味わいを改良しているのですが、春夏向けの特徴は「すっきり飲めること」です。逆に秋冬は濃いめにしています。冬場は濃い味付けの食べ物も多くなるため、すっきりし過ぎていると薄く感じられてしまうからです。
こうした組み合わせで味わいをデザインしていきますが、農作物ですから年によって採れる茶葉の品質は違いが出てきます。茶葉の品質が全体的に恵まれる年もあれば、うま味が少ない年もある。その年の茶葉でいかにバランスの良い味わいをつくっていくかになりますね。
冬はすごく寒いこと。うま味をぎゅっと蓄え、根っこに凝縮するようなイメージでしょうか。寒さを耐えて3月以降にじわじわと気温が上がり一気に芽吹くと、うま味成分たっぷりのいい茶葉になります。もちろん、雨も大事ですし、寒暖のメリハリは大切です。

伊藤園は全国の茶農家と提携。日本の荒茶生産量の25%を扱っている
以前、静岡で春先に霜が降り、畑が全部ダメになったことがありました。伊藤園は全国に契約農家がありますから1ヵ所で収穫できなくても、製品供給に影響することはありません。ですが、ショックでしたね。緑の葉が霜のせいで赤くなってしまい、そうなるともう刈り取りができない。天候は仕事を離れている時でも気になります。
配属当初は味の違いがわかりませんでした
専門部隊がありまして、5年10年にわたって毎日茶葉をチェックすることで感覚が研ぎ澄まされてくるんですよ。
お米を想像するとわかりやすいと思いますが、品質チェックではまず、葉の色つや、輝きがないもの、色素が薄いものは外す。実際に飲んでみて「ちょっと違うな」というものも外す。
頭の中にさまざまな茶葉の特徴が入っていますし、抽出温度や時間の差でどんな味わいになるかも入っている。異なる茶葉でも「ブレンドしたらこういう味になる」とか「うま味を立てたいならこれくらいの温度で抽出する」といったことも経験値でわかりますね。

「専門部隊は頭に茶葉のあらゆる情報が入っている」と安田さん
もちろん、最初は全然わかりません。私自身、緑茶ブランドチームに配属された当初は、味わいの違いがわかりませんでした。
試飲の際は先輩のコメントをそのままなぞり「渋みがありますね」と言ってみたり、「これは香りがないですね」と答えたり。だから、たまに最初に聞かれると困るわけです(笑)。適当に答えるとスパッと「違う!」と言われます。
結局、訓練というのか、毎日3年くらい続けていくうちに、ようやく微妙な違いが感じられるようになりました。
発売17年経った『お〜いお茶 濃い茶』が機能性表示食品となって急伸
緑茶飲料分野における年間売上げ世界一ということで2018年から3年連続でギネス認定されました。国内飲料市場においても「お~いお茶」ブランドの販売実績は2020年もNO.1を維持しており、これは2002年のデータ開示以来、19年連続となります(※SRI無糖茶飲料市場2020年1月~12月/売上本数)。
緑茶飲料市場が拡大したのは2000年初頭です。2000年時点での市場規模は2170億円でしたが、2005年には4470億円と倍増。同時期にさまざまな緑茶ブランドが登場したことで、無糖飲料市場としても広がりました。
その後、リーマン・ショックや震災でやや落ちたものの、昨今は勢いが戻ってきて2019年は「2005年を超えるか?」と予測されていたんです。2020年はご存じの通り、コロナ禍でもう一歩届きませんでした。2022年以降にはかなり期待をしています。

「無糖飲料のシェアは6割までいくのではないか」と安田さん
というのも、緑茶飲料市場にはまだまだ可能性があるからです。
『お~いお茶』の前身である『缶入り煎茶』を発売した1985年当時、有糖飲料と無糖飲料のシエアは100:0でした。それが2000年には70:30になり、直近の2020年は無糖飲料のシェアが53%になりました。おそらく近い将来6割くらいまではいくのではないかと思っています。
海外での展開もこれからです。アジアやアメリカでも、有糖飲料から無糖飲料への流れが始まっている。特にアメリカでは緑茶を飲むと「頭がシャキッとする」とクリエイティブサポート飲料のような扱いになってきている。「美味しさ」と「健康」という面で本当に潜在能力が高いと感じています。
昨年は1.5倍、今年に入っても3割増の伸び率です。『お〜いお茶 濃い茶』は2004年に発売した商品ですが、2019年に“体脂肪を減らす”という機能性を表示したんですね。
食事中の脂肪の吸収を抑制する“ガレート型カテキン”を含む機能性表示食品として、今までと味わいを変えずに同一の希望小売価格で発売しました。急激に上がった数字は翌年になると落ちてしまうことも多いのですが(笑)、濃い茶はそうした表面的な売れ行きではない気がしています。

『お〜いお茶 濃い茶』 体脂肪を減らす表示で1.5倍のヒットに
機能性表示商品としては、ほかに『お~いお茶 お抹茶』を展開していますが、こちらは認知機能に着目しました。抹茶に含まれるテアニンと茶カテキンは、注意力や判断力などの認知機能の精度に有効という研究結果が出ています。
モチベーションはお茶の可能性です。それが一番大きいと思います。『お〜いお茶』の担当になって15年以上になりますが「まだまだ上を目指せるはず」ーーそう実感したのは実は、比較的最近のことなんです。
課題はあります。ターゲットは全世代ですが、20代、30代以下の若い層との接点をもっとつくっていかなくてはと思います。同時にもっと美味しくさらに美味しく、です。伊藤園という会社はモノづくりに妥協しませんからしんどいことはたくさんあります(笑)。
ですが、健康面での訴求にしても海外にしても本当にこれからです。市場はもっと大きくなる。お茶に関する健康についてのフォーラムや研究発表を見るにつけ「お茶はすごい」と感慨深い気持ちになります。
30年以上続いてきた『お~いお茶』にはもっと先の未来がある、そう思いながら仕事をしていますね。

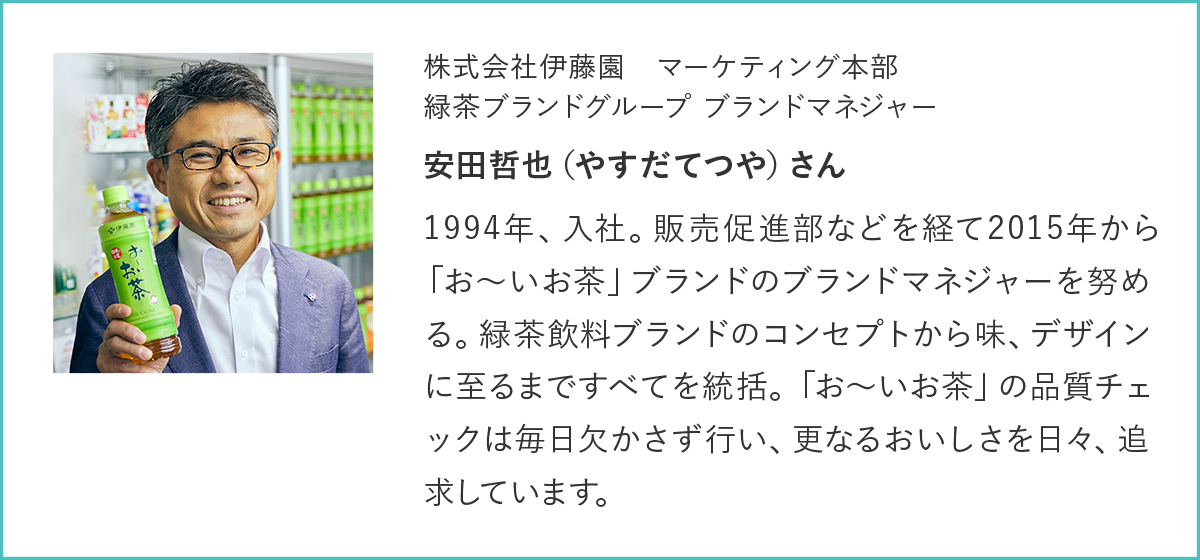 伊藤園
伊藤園
