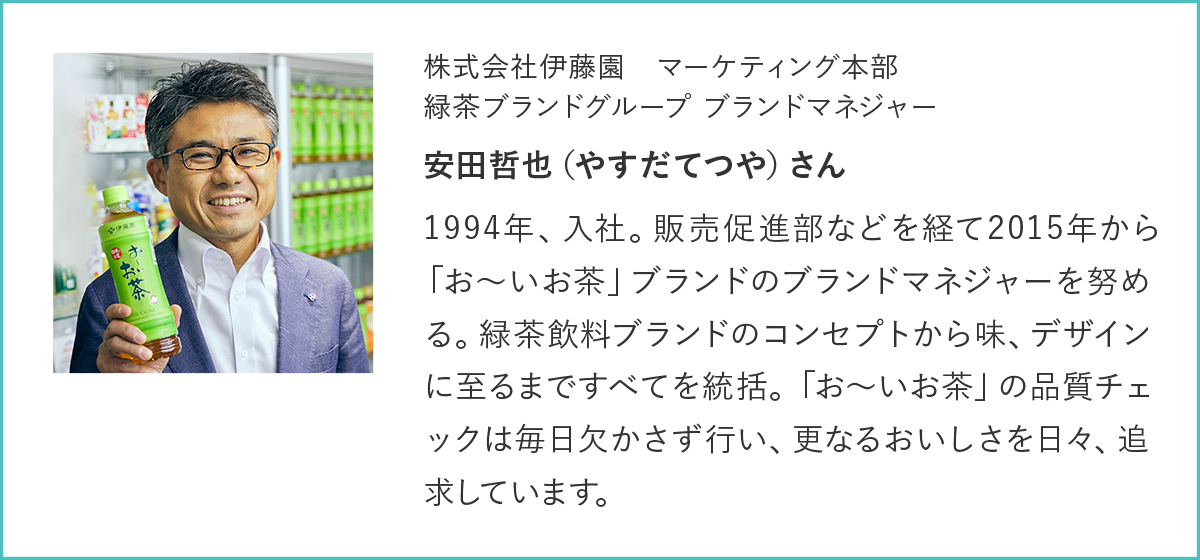文字通り、日本の緑茶市場をけん引してきた同ブランドだが「海外を含め無糖市場の広がりを考えても可能性はまだこれから」という。ブームの“濁り”茶に参入しない理由や匠の技そのものである味づくりへのこだわりまで、伊藤園マーケティング本部の安田哲也さんに語ってもらった。
『お~いお茶』への名称変更で売上6億から40億円へ!
想像しがたい数字かもしれませんが、今でも毎年春と秋との改良では1000通りほど試作をしています。『缶入り煎茶』は世界で初めての緑茶飲料です。当時は緑茶飲料をつくること自体が難しかったので、そのくらいは行っていたのでしょうね。

伊藤園マーケティング本部・緑茶ブランドグループブランドマネジャーの安田哲也さん
お茶づくりは酸化、劣化との闘いです。先人は「宵越しのお茶は飲むな」と言いましたが時間が経つと色みも落ちるし、味も落ちる。しかし、当初は「味が落ちる原因」さえわからないままでスタートしました。
酸素が原因だとわかった後もその壁を越えるために、試行錯誤の繰り返しです。原理としては、お茶を満タンにして缶にフタをすれば無酸素にはなりますが、どうしても上部に酸素が残ってしまう。
そこで水に溶けにくい窒素を吹きかけることで酸化を防いだ。この技術が世界初の緑茶飲料『缶入り煎茶』の開発につながりました。
そもそもの背景は「日本人のお茶離れをどうにかしたい」という想いでした。70年代はコンビニエンスストアやファストフードができ、また飲料の自販機も増えてきて生活が一気に多様化した時代です。
それに伴い、家庭でのお茶の消費量も減っていた。急須を使わずに気軽に飲めるお茶があれば、市場を再開拓できるのではと考えたわけです。
一方で「お茶はタダで飲むもの」という印象を拭えなかったのも事実です。当時、炭酸飲料などはすでに普及しており、有糖飲料と無糖飲料の市場比率は100対0。緑茶飲料を置くようなお店は少なく営業は苦戦したと聞いています。

『お~いお茶』の前身となった『缶入り煎茶』。お弁当と売るなどで販路を開拓した。
転機の一つは、電車の駅のホームでの販売です。ある時、新幹線に乗った社員が「お弁当」と「プラスティック容器のお茶」が一緒に売られているのを見てひらめいた。「お弁当と一緒なら売れるのでは?」。
それを機に最初は街のお弁当屋さんに置いてもらい、徐々にスーパーやコンビニエンスストアへと販路が広がっていったいきさつがあります。
“煎茶(せんちゃ)”が読めないという声が挙がったんです。
急きょ大学生向けに『日本茶を何と呼ぶか?』のアンケートを取ったところ、予想に反し“煎茶”は4位。1位は”緑茶“でした。”煎茶“は業界では一般的な名称でしたが、要するに消費者との認識がかけ離れていたんです。
「ぜんちゃ? まえちゃ?」「ほんとにお茶なのかな?」という時点で、手にとってさえいただけません。名前を覚えてもらえない、読めないようなブランドが売れないのは当然です。
新しいネーミングは消費者に語りかけるような、覚えてもらえやすいものを意識しました。当時の伊藤園のCMで俳優の島田正吾さんが『お~いお茶』とおっとりと呼びかける場面がありそれを採用。結果的に売り上げは大きく伸びました。
『缶入り煎茶』の時代は年6億ほどで推移していたところ、『お~いお茶』に変更した翌年には年40億円を突破しました。その後、2000年頃までは競合もなく毎年2ケタで成長していましたね。
お茶の“濁り”がブームになっても、うちだけはやりません
90年にペットボトル市場に乗り出しました。ただ、この開発にもかなり苦労しています。

「お~いお茶」は世界初のペットボトル緑茶
緑茶は抽出したままだと、細かい茶葉が残り沈殿します。沈殿物がある状態では透明のペットボトルでは見た目にもよくないですし、味の劣化につながってしまいます。
そこで、研究の末に開発したのが「沈殿物」を除去する製法でした。この技術は伊藤園にしかないもので、水を100とすると『お~いお茶』の透明度は97から98。美味しさや香りが引き立つ透明度です。
他社さんは「沈殿物」を逆手にとり「濁り」として訴求していますが、うちとしては「沈殿物があると美味しさを保てない。味が損なわれる」という考えでやっています。
「急須で入れるとお茶って濁るよね?」という声もあるかもしれません。けれど、清涼飲料水のお茶と急須のお茶は実はまったくの別物です。急須で飲むお茶であれば濁りもうま味と感じますが、清涼飲料水はどのような場面でも美味しく飲めるのが必須条件だと思っています。
いつ飲んでも美味しい、キャップをあけた瞬間が一番美味しい緑茶を開発
クリアなお茶の美味しさにこだわった商品提供は「お~いお茶」ブランドの強みです。その点は長年のお客様調査において自負していることでもあります。味が濃い飲み物は水が飲みたくなりますが、同様に水が飲みたくなるお茶もある。やはり、それだと良くないわけです。

『お~いお茶』ブランドは30年以上クリアな味を展開してきた。
ただ、開発の際は“できたて”で「良い」「悪い」の判断はせず、経過を見ます。お客様の手元に届いたときにいちばん美味しい状態となるような品質にしています。もちろん、流通している期間(賞味期限内)は味が落ちるということはありません。
後編では、引き続き味づくりや緑茶市場の展望についてお話ししたいと思います。