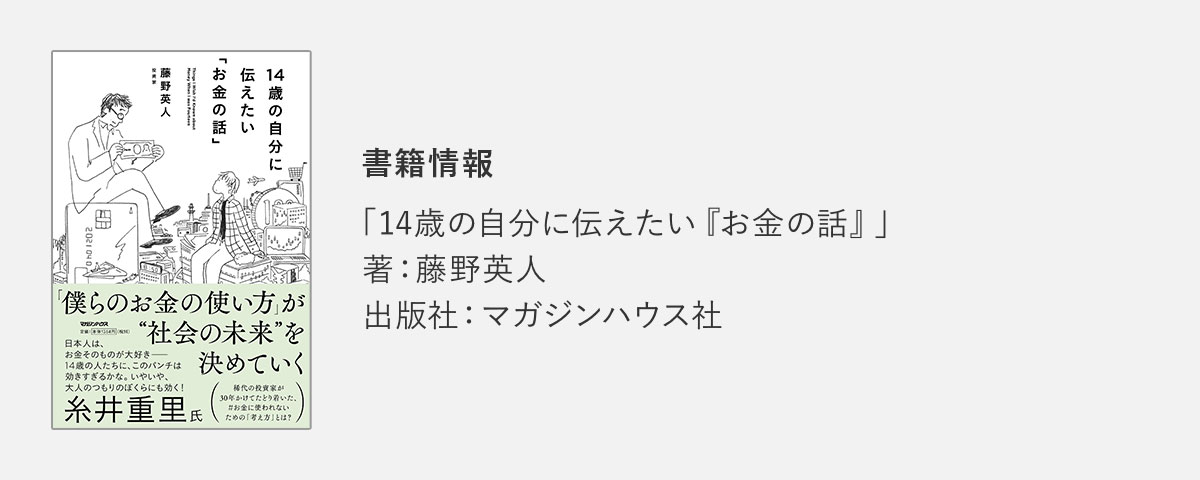「お金とは何か?」という問いに関連して「経済」についても、少し話をしようと思います。
君は「経済とは何?」と聞かれたら、どう答えるでしょうか? 君は結構勉強ができたから、学校や塾で習ったことをいろいろ話してくれるかもしれない。
でも、教科書に載っている「経済」はお金を稼いで自由に使えるようになってから初めて関わり始めるもので、まだ働いていない自分には関係ないと思っていないでしょうか。
もしそうだとしたら、そのイメージは今日から捨ててほしい。経済は大人だけのものじゃない。子ども、もっと言えば、今この瞬間にオギャーと生まれた赤ちゃんにだって深く関わるものなのです。
僕たちはこの地球上で生きているだけで、大いに経済に貢献しています。
たしかに、高給取りでたくさん税金を納めている人が社会全体の経済にもたらすインパクトは強いでしょう。けれど、1円も稼いでいない14歳だって、立派な経済人なのです。
例えば、君が着ている服、さっき飲んだペットボトルのジュース、夕ご飯に食べる予定のオムライス。それらは全部、もとは誰かがつくった商品だったはずです。
それを君の親や君自身が買って、自分のものとして使っている。使ったお金は君が稼いで得たお金ではないかもしれないけれど、君は〝消費者〟として、そのお金の流れのきっかけを生み出した張本人なのです。
つまり、君がこの世界に生まれなければ動かなかったお金があるということ。そう考えると、経済という言葉がぐっと身近に感じてきませんか?
君が生きているおかげで、存在している会社はたくさんあると思っていい。
今日着ているシャツが3000円だったとして、その3000円はシャツを売っていたお店やつくっていたメーカー、そのほか関係する会社にとっての「売り上げ」になります。
売り上げのお金を元手にして、その会社で働く人たちに給料が支払われ、さらに新しい商品を生み出す原資として使われて、また君の手元に来シーズンの服がめぐってくる。こういった経済のサイクルは〝消費〟がなければ動き出しません。
この世に生まれてから14年間、完全な自給自足で、誰とも交流せずに過ごしてきたという中学生はいないでしょう。人やモノと関わっている時点で、立派に「経済に参加している」と言えるのです。
中学生どころか、生まれたばかりの赤ちゃんだって、ミルクを飲み、オムツを代えてもらい、泣けばお気に入りのオモチャを差し出されます。これだけでも、ミルクをつくる会社、オムツをつくる会社、オモチャをつくる会社の売り上げを支えている。赤ちゃんが一つの産業を成り立たせているのです。
僕は世の中の誤解を解きたい。
「働いて稼がなければ経済に参加していない」なんて大間違いだと、声を大にして言いたい。
専業主婦・主夫の人が「私は働いていないから、社会に参加していない」と言うのを聞くと、つい「そんなことはありませんよ」と話をしたくなります。
専業主婦・主夫という〝仕事〟は、働くことに集中するパートナーに代わって、その人の分まで家事や育児を担うという生き方なのだから、それだけでも十分に立派な社会参加です。
また、もし家事や育児をしていなかったとしても、生きて消費をしているだけで、家族以外のたくさんの人を支えていることになります。
お年寄りだって同じです。「定年退職したから、もう世間の用なしだよ」なんて言っているおじいちゃんに対しても、そうではないと訴えたい。
もっと言えば、世間で冷ややかな視線を浴びがちなニート(就学・就労をせず、職業訓練も受けていない状態)にあたる人たちも、消費者としての社会参加は日常的にしています。
寝たきりで身体の自由がきかない人であっても、治療や療養を通じて経済に深く関わっています。
消費がなければ、経済は動かない。
人間は生きている限り、無条件で誰かを支えている。そこには年齢も性別も就労の有無も関係がない。すべての人が、誰かを支えている。この相互扶助の考え方、つまり、互いに助け合う「互助」の関係こそが「経済」の基礎です。
経済とは、人と人が支え合う営みのことなのです。