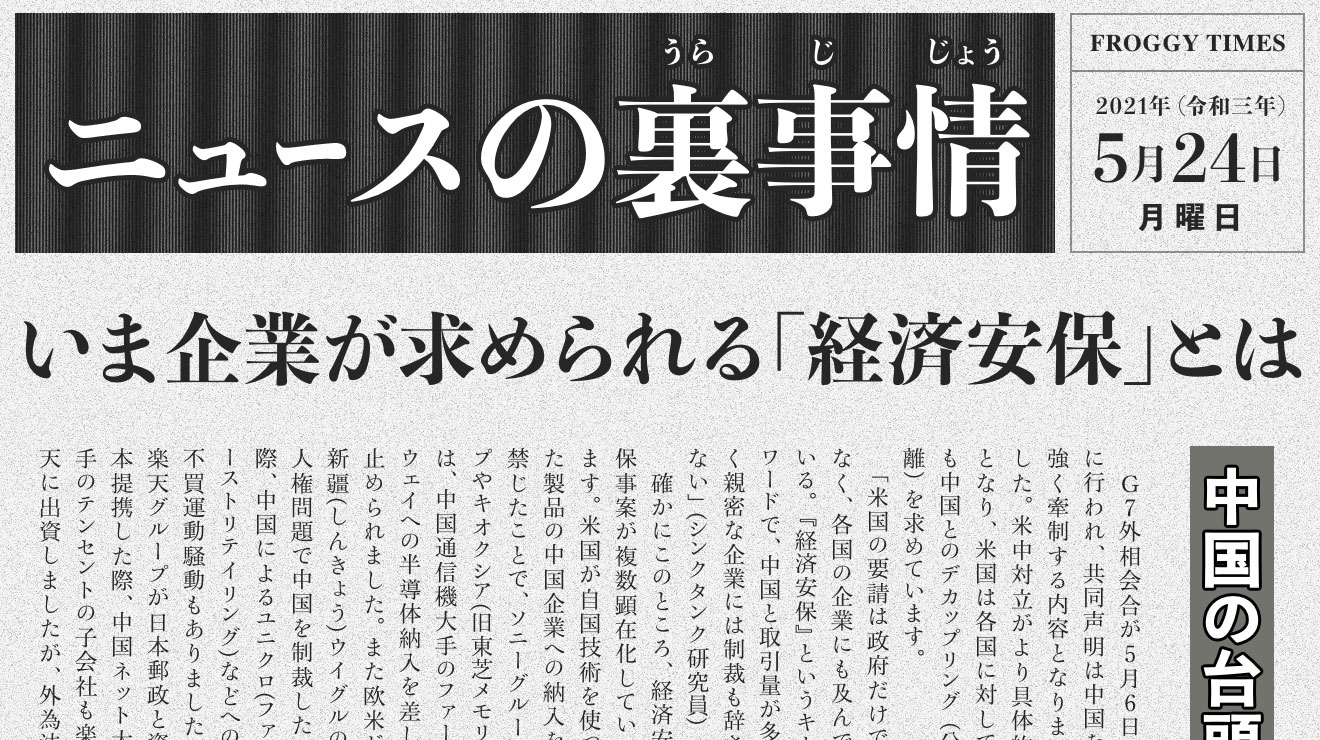テレビや新聞で取り上げられたニュースの裏側を解説する本連載「ニュースの裏事情」。今回は、新たな米中対立による企業への影響についてご紹介します。
中国の台頭による国際情勢の変化が背景
G7外相会合が5月6日に行われ、共同声明は中国を強く牽制する内容となりました。米中対立がより具体的となり、米国は各国に対しても中国とのデカップリング(分離)を求めています。
「米国の要請は政府だけでなく、各国の企業にも及んでいる。『経済安保』というキーワードで、中国と取引量が多く親密な企業には制裁も辞さない」(シンクタンク研究員)
確かにこのところ、経済安保事案が複数顕在化しています。
米国が自国技術を使った製品の中国企業への納入を禁じたことで、「 ソニーグループ 」やキオクシア(旧東芝メモリ)は、中国通信機大手のファーウェイへの半導体納入を差し止められました。
また欧米が新疆(しんきょう)ウイグルの人権問題で中国を制裁した際、中国によるユニクロ( ファーストリテイリング )などへの不買運動騒動もありました。
「 楽天グループ 」が「 日本郵政 」と資本提携した際、中国ネット大手のテンセントの子会社も楽天に出資しましたが、外為法の外資規制に抵触するとの指摘が入って払い込みが延期となり、先の日米首脳会談に先立ち、日本政府が米国に経緯を説明するという一件もあったばかりです。
また政府は「 トヨタ自動車 」や「 NEC 」など50社を集め、官民で量子技術を研究する協議会を立ち上げると報じられました。日米首脳会談での声明に盛り込まれたもので、これも中国を意識したものだとされています。
「経済安保」がある種のブームに
このような動きの中、産業界も態勢づくりに取り組んでおり、経済同友会は4月21日、経済安保に関する提言を発表。提言では「日本企業にとって、米中両国の貿易管理令における域外適用も含むルールは、従業員の刑事訴追、場合によっては拘束にも及ぶ可能性」もある、と危機感を高めています。
その中で「 三菱電機 」は、いち早く昨年10月に経済安全保障統括室を新設。最近の報道では、政府が企業に経済安保担当役員の設置を求めるとも伝えられました。
「三菱電機の経済安保担当常務は元資源エネルギー庁長官の日下部聡氏。企業の経済安保担当役員は経産省や外務省などの天下り枠を増やすことも念頭に置いているのだろう。今年2月に公安調査庁は「経済安保」対策チームを立ち上げ、業容拡大した。官僚の間で経済安保はある種のブームになっている」(前出・研究員)
グローバルで活躍する企業の対中・対米を意識した行動に、今後も注目が集まりそうですね。
(出典:日本証券新聞)