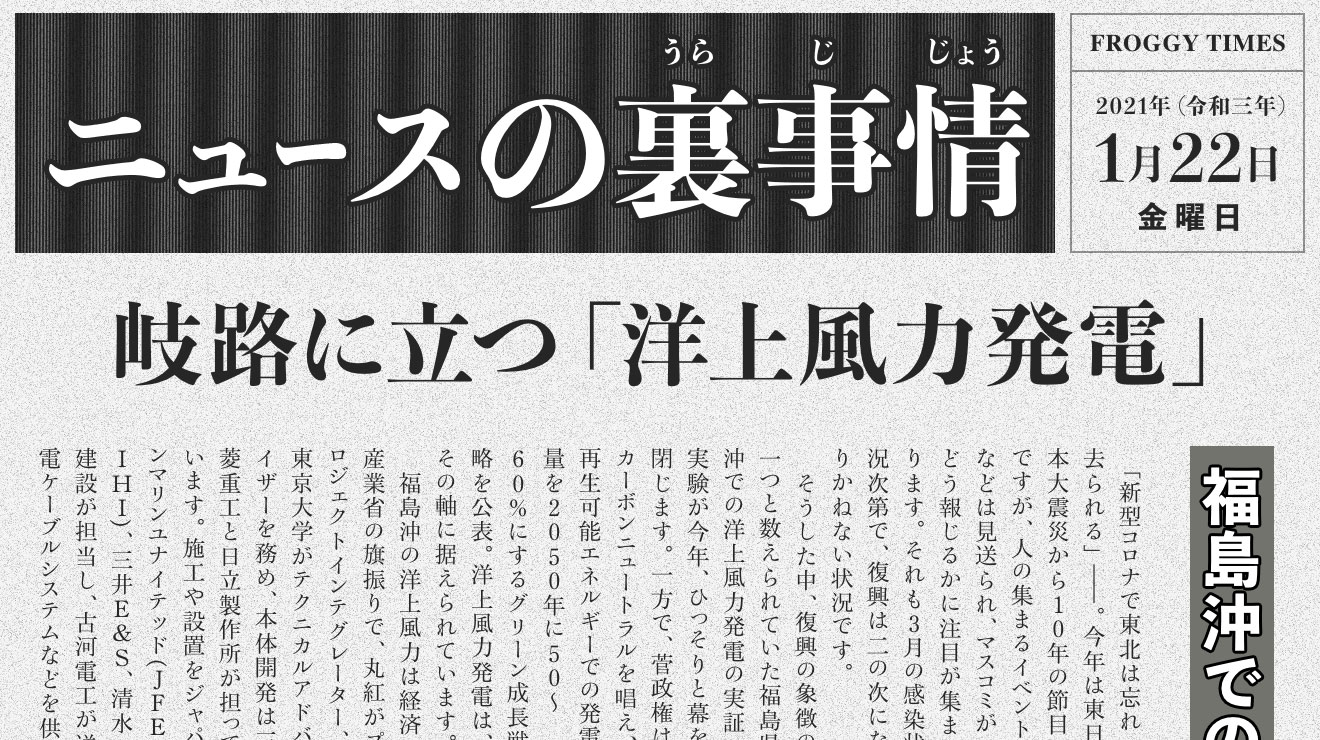テレビや新聞で取り上げられたニュースの裏側を解説する本連載「ニュースの裏事情」。今回は、岐路に立つ「洋上風力発電」に関するニュースについてご紹介します。
福島沖での知見活用は東北復興の一助に
「新型コロナで東北は忘れ去られる」――。今年は東日本大震災から10年の節目ですが、人の集まるイベントなどは見送られ、マスコミがどう報じるかに注目が集まります。それも3月の感染状況次第で、復興は二の次になりかねない状況です。
そうした中、復興の象徴の一つと数えられていた福島県沖での洋上風力発電の実証実験が今年、ひっそりと幕を閉じます。一方で、菅政権は2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」を唱え、再生可能エネルギーでの発電量を2050年に50~60%にするグリーン成長戦略を公表。洋上風力発電は、その軸に据えられています。
福島沖の洋上風力は経済産業省の旗振りで、「 丸紅 」がプロジェクトインテグレータ、東京大学がテクニカルアドバイザーを務め、本体開発は「 三菱重工 」と「 日立製作所 」が担っています。
施工や設置をジャパン マリンユナイテッド( JFE ・ IHI )、「 三井E&S 」、「 清水建設 」が担当し、「 古河電工 」が送電ケーブルシステムなどを供給。
「 日本製鉄 」は本体の厚板や係留チェーン用の棒鋼といった鋼材ソリューションを提供し、みずほ情報総研( みずほFG )が基本構想の策定を担いました。
課題もあるが、ポテンシャルは高い「浮体式」
日本の国土は狭いですが、実は排他的経済水域では世界6位の面積があり、洋上風力設置のポテンシャルは高いと言えます。しかし、水深が深いため、設備を海底に固定する着床式ではなく、海上に浮かべる浮体式が主とならざるを得ません。浮体式はコストも掛かり、技術的にもまだ開発過程にあります。
「福島沖には日立の出力2000キロワットと5000キロワット、三菱重工の7000キロワットの3基を設置したが、陸上での稼働実験が不十分なまま急ぎ設置したため、計画通りの稼働率を得られなかった。アンカーと本体を結ぶチェーンの強度も想定より必要だったため、設置作業も難航するなど、試行錯誤でうまくいかなかった」(経済ジャーナリスト)
採算化が見込めず、一昨年から撤退を検討し昨年末、21年度予算に撤去費50億円が計上され、正式に撤退が決まりました。
「そんな中、政府は洋上風力を成長産業として育成する方針を示している。国内には発電機、増速機、ベアリング、ブレード用炭素繊維、永久磁石などで潜在的競争力があり、あとは国内にはない風車製造拠点を整備する計画だ」(前出・ジャーナリスト)
新規の洋上風力産業ビジョンにおいて福島沖での知見を忘れずに活用することは、東北復興の一助にもなるはずです。
(出典:日本証券新聞)